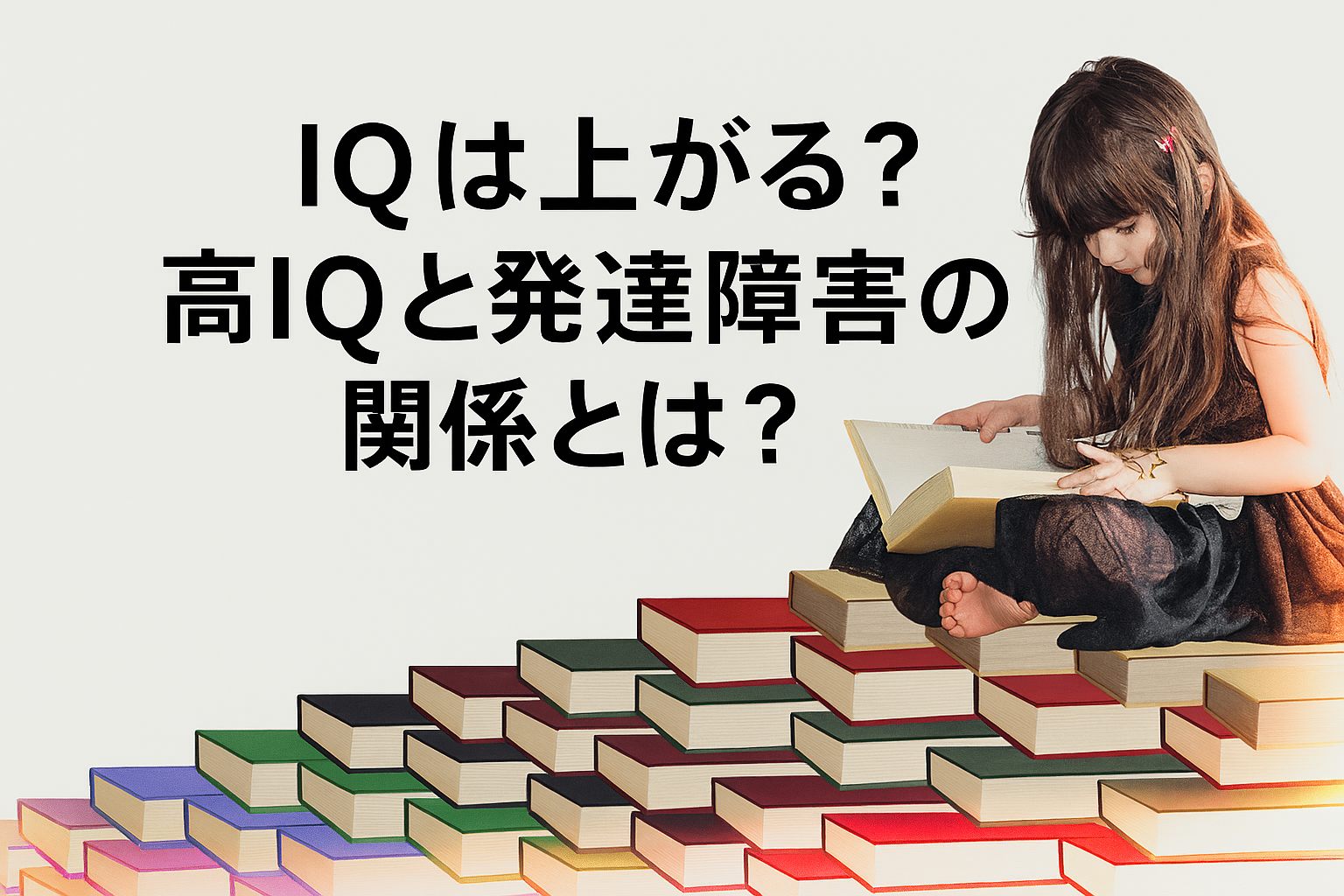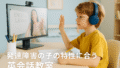<2025年5月更新>
本記事は、WISCと発達障害、IQの関係についての第2弾です。
第1弾はこちら↓
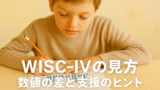
本記事をお読みいただくと、
について知って頂くことができます。
IQについてわからないことを解消し、検査結果を正確に理解することは、
これらのことに役立ちます。
<関連記事>特性に合わせた習い事について

<関連記事>WISCの言語理解が高いお子さんにおすすめの英語学習について
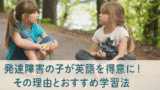
1. WISC‐Ⅳで全検査IQが高くても発達障害と診断される場合がある?
<結論>
発達障害を持つ人には様々なIQの人がおり、全検査IQが高くても、発達障害と診断される場合があります。
「発達障害=IQが低い」ではない
「発達障害を持つ人は知的な遅れがある」と誤解されている場合がありますが、
全検査IQが一定の数値以下である
4指標の数値間に差がある(得意・不得意の凸凹がある)
で両者は異なります。
*4指標の数値に差がある場合でも、そのことだけから発達障害と診断されるわけではありません。数値の差も判断の要素ではありますが、生活上の困りごとを総合的に見て診断されます。
発達障害は、「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」というWISC‐Ⅳの4つの指標※の間に差がある、アンバランスさから生ずるものであり、4つの平均である全検査IQが高い人でも、最も高い指標と最も低い指標との間に大きな差(ディスクレパンシー)があれば、発達障害と診断される場合があります。
※4つの指標について詳しくはこちらをご覧ください↓
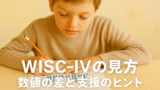
「ギフテッド」の中にも発達障害を持つ人がいる
全検査IQが130以上でIQが特に高く、生まれつき特定の能力が突出している人を、「ギフテッド」と呼ぶことがあります。
このギフテッドと呼ばれる人たちの中にも、発達障害を持つ人がいます。
ちなみに、ギフテッドには
- WISC‐Ⅳの4指標の間にさほど差がない「英才型ギフテッド」
- WISC‐Ⅳの4指標に大きな差があり発達障害の特性を持つ「2Eギフテッド」
の2種類の人がいます。
2Eギフテッドについては、こちらの記事もどうぞ↓
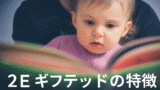
2. IQが将来的に上がることはあるのか?
IQは本来、先天的な能力を数値化したものと考えられており、もともと持っているIQが後に上がる可能性は低いと考えられてきました。
しかし、現在では専門家の中でもIQは後天的に変化する場合があるという見解が有力で、中には大人になってもIQが変化するという専門家もいます。
IQは生まれつきで一生変化しない、というのがこれまでの科学の世界における「常識」でした。ですから、たとえば子どもの頃にIQを調べれば、今後の成績や就労状況が予測できると言われていました。 IQの検査結果が、子どもたちの将来を左右することすらあったのです。
しかし、これをくつがえす事実をロンドン大学のプライス教授の研究チームが発見し、2011年に、権威あるイギリスの科学誌ネイチャーに報告しました。研究チームは10代の男女を集め、およそ4年の間隔をあけてIQテストを2度行い、その間に思春期の青年たちのIQが大きく変化することを突き止めたのです。言い換えれば、IQは生涯変わらないわけではなく、成長に伴って変化しうるのですね。
見えてきたこと ~世界の子ども研究~ 今を知る | 東京ティーンコホート (umin.jp)
この後ご紹介する通り、実際に息子も幼少期の検査と比較すると、現在の全IQはかなり上昇しています。
それではどのような場合に、後にIQが上がると考えられるのでしょうか?
ケース①特性の影響でIQが低く出ていた場合
まず考えられるのが、幼児期に強かった発達特性の影響で本来より低いWISCの数値が出ていた場合です。
- ADHDの特性により、(興味がないため)検査に集中できない、気が散って説明を聞けない
- ASDの特性により、マイルールへのこだわりが強く、問題の趣旨に沿った回答ができない
- ASDの特性により、完璧主義で間違えるのを極度に恐れ、自信がない問題には解答しない
以上のような場合が考えられます。
<我が家の実例>
上の3つは、実は息子のIQが上昇した際に医師から指摘されたことです。
息子は3歳時の新型K式発達検査でDQ90であったのが、小学校高学年頃のWISCでは全検査IQ140前後でしたので、(発達検査と知能検査は数値の評価の仕方が違いますが)単純に比較すると50近く上がったことにいなります。
息子の場合は、小さい頃に特性が強く出て、色々な活動に支障が出ていたので、特性の影響で本来持っていた能力より数値が低く出ていたのかなと思います。
幼少期から主治医に「解っていないようで、意外と理解しているからね。」と言われたり、療育の先生に「頭がいいと思う。」と言われましたが、素人目には幼少期はIQが高いように見えませんでした。
特性によってIQの数値が下がっている場合は、小学校高学年くらいまでには数値が落ち着き、それ以降はあまり変わらない場合が多いようです。
これは、ADHDの多動がその頃にはある程度落ち着いたり、ASDのこだわりも成長や経験により少し柔軟になってくることと関連しているのかもしれません。
ケース②幼児期の働きかけ
二つ目は、幼児期に色々な働きかけをすることにより、IQに影響があるのではないかという考え方です。
一般に年齢が低いほど働きかけの効果が大きいのではないかと考えられているので、良い影響を与えるなら小さいうちほど良いと言うことになります。
保護者による働きかけ
例えば…
と言われています。
このように、子供の持っている能力を最大限に高めていくことで、IQを伸ばすことができるのではないかと考えられています。
コグトレ
児童精神科医の先生に紹介していただいたのは、こちら。
知覚推理や処理速度のアップが期待できます↓
 | 医者が考案したコグトレ・パズル 親子でいっしょに学ぼう! [ 宮口 幸治 ] 価格:1430円 |
ピアノ
ピアノは、言語に関係する神経束が太くなったり、記憶に関係する海馬の機能も良くなることから、IQアップに役立つ可能性があります。
発達障害を持つ子とピアノの関係については、こちらの記事もどうぞ↓

ケース③環境が改善され、本来の能力を発揮
三つ目は、合わない環境に置かれていた子が、自分に合った環境で落ち着いて勉強や生活ができ、本来の能力を発揮できるようになった場合です。
例えば
- 学校の担任の先生と相性が悪い
- 人間関係が不穏で落ち着いて勉強ができない
というような場合。
本来学ぶべきものが学べず、伸ばすべき能力が伸ばせなくて、その間のIQが低く出てしまう、ということがあります。
その後、本来の能力を伸ばせる環境、本人に合った学習環境に置かれたとき、IQが改善されるというのがこのケースです。
<関連記事>通常学級での支援・学校との連携について

ケース④二次障害が改善
様々な理由で、うつ状態などの二次障害が生じた場合、二次障害が理由でIQが下がってしまう場合があります。
二次障害によって本来できる活動が難しくなるためです。
二次障害が改善すると本来の力が発揮できるようになり、IQの数値が上がるケースがあります。
「IQは変化するのか?よくなるのか?」ということですが、答えは変化します。
例えば、認知機能が下がる可能性のある病気に罹患した際は、IQが下がることがあります。
うつ病や統合失調症などの悪化時は、「頭が回らない、ぼおっとする」とおっしゃる方も多いですが、一過性に知的能力が下がる可能性があります。その際の心理検査結果は通常時よりも下がります。
IQは変化するのか?IQ改善例。 (meiekisakomentalclinic.com)
結局、本来の能力が発揮されただけという可能性も…
ここまで読んで下さり、気づかれた方がいらっしゃったかもしれませんが、「IQが上がる場合」でご紹介したパターンの多くに、
「本来持っていた能力を発揮できた」ことによるIQの上昇
という共通点があります。
IQが上がる場合②でご紹介したように、「幼少期に英才教育をしてIQを伸ばす」ということは可能なのでしょうが、それでも先天的なものを超えて数十以上大幅にアップ…ということは難しいのかもしれません。
ただ、大幅なアップはできなくても、本人が本来の能力を発揮できるように、環境を整えたり、二次障害を防ぐ…という工夫なら、比較的取り組みやすいのはないでしょうか。
いかがでしたか?
この記事が、WISCを受けた方、受けることをご検討中の方のお役に少しでも立つことがあれば嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。