<2025年10月更新>
発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム)やグレーゾーンのお子さんの中学受験における【学校選び】について悩んでいませんか?
私立中学校を受験する際の注意点や、子どもの特性に合った学校の選び方を、実際の体験をもとにブログ形式でまとめました。

中学受験をさせたいけど、どんな学校を選べばいいんだろう。

学校を選ぶ際に気を付けるポイントは?
こんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、発達障害を持つ子どもの中学受験に向けて
- 学校選びでチェックすべきポイント
- 特性に合った学校のタイプとは?
について、体験を交えてご紹介します。
【PR】発達障害・中学受験に対応。
経験豊富な先生がしっかりサポート👇
ASD+ADHDの特性を持つ男子高生の母で、兼業ライターです。
息子は中学受験をして、現在、私立中高一貫校に元気に通っています。
息子の中学受験では、発達障害の子に合った学校の情報がなかなか得られず苦労した経験から、保護者の方に役立つ情報発信を目指しています。
<関連記事>発達障害の特性に合った塾選び・受験スタイル
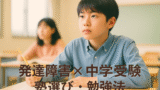
学校選びのポイント
発達障害、グレーゾーンの子供たちは、どちらかというと得意・不得意がはっきりしていて、「なんでも平均的にできる」というタイプは少ないですね。こうした特性を踏まえた中学校選びは、とても大切なポイントになります。
中学受験は、そんな凸凹のある子供たちにとって、さまざまな特色を持つ教育環境や教育方針の学校の中から、特性に合った中学校を選択できるという点が大きなメリットと言えるでしょう。
では、学校を選ぶときには、どんなことに気を付ければいいのでしょうか。
1. 子どもの特性を整理する視点
まずは、お子さん自身の特性を整理することから始めてみましょう。
これまでのお子さんの様子をふり返って、以下のような点を書き出してみると、中学校選びの方向性が見えてきます。
- 興味のあること、得意なこと
- 学校で困っていること、サポートが必要なこと
- お子さんの好きなタイプのお友達
- これまでうまくいった環境の特徴
お子さんに合った教育環境を考え、それに近い中学校を探していくことで、特性に合う学校が見つけやすくなります。
1-1. 好きなこと・得意なことを洗い出す
例えば…
・鉄道好き、将棋好き、eスポーツが好き
→ 該当する部活のある学校へ
・プログラミングに興味がある
→ カリキュラムがある学校へ
・英語が得意
→ 英語教育に力を入れている
→交換留学制度のある学校へ
得意なこと、好きなことを思いきりできる環境があれば、学校に通うことが楽しくなりそうですね。
高校受験のない中高一貫校に入ることができたら、その中でお子さんが思いきりやってみたいことは、いったい何でしょうか?
中学校選びを考えるときには、こうした視点も大切です。
1-2. 苦手なこと・支援が必要なことを明確に
今、学校でお子さんが困っていることは何でしょうか?
サポートが必要なことはありますか?
中学校入学後に個別のサポートをお願いすれば対応してもらえる場合もありますが、はじめからお子さんが困りにくい環境を選ぶという考え方も大切です。
例えば…
・プリントをすぐになくす、提出物が出せない
→ 配布物や提出物をロイロノートやGoogle Classroomで管理できる学校、または先生の指導が手厚く面倒見のよい学校を検討するとよいでしょう。
・水泳がどうしても苦手
→ 私立中高一貫校の中には、プールのない学校もあります。プールがないだけでも、夏季の通学が精神的に楽になるお子さんもいます。
ただ、子どもの困りごとは、成長とともに変わってくることがあります。
今は苦手なことでも、学年が上がるにつれて自然に解消することもある一方で、環境が変わって新たに困ることが出てくる可能性もあります。
身近に児童精神科医や心理士、信頼できる療育の先生がいる場合は、次のように聞いてみるのもおすすめです。
「うちの子のようなタイプは、中学生になって、どんなことでつまずきそうですか?」
専門家の視点を取り入れることで、学校選びの判断材料が増えます。
入学後の個別サポートについては、こちらの記事も参考にしてください。

1-3. 相性の良い友達の特徴を整理
中学受験をすると、大体同じくらいの学力レベルの子が同じ学校に入学します。
そのため、中学受験をしない場合よりも、自分と似たタイプの子に出会える可能性が高くなります。
特に難関校では、生徒の精神的年齢が比較的高く、それぞれの個性を尊重するタイプの子が多い傾向があります。
お子さんが気の合うタイプのお友達は、どのような子でしょうか?
中学校選びの際には、学力やカリキュラムだけでなく、こうした「友人との相性」も意識しておくと良いですね。
1-4. 過去に合っていた環境を参考にする
これまで、比較的順調に活動ができた環境について整理してみてください。
- 大好きな習い事に時間を忘れて没頭していた
- ○年生の担任の先生が□□□のサポートをしてくれたので、落ち着いて過ごせた
- △△君とは仲良く遊ぶことができる
こうした「うまくいっていた場面」には、お子さんにとってのヒントが隠れています。
何が良かったのかを改めて考えてみると、中学校選びの方向性がより具体的に見えてきます。
2. 発達特性に合った学校タイプを知る
私立中高一貫校の中で、発達障害のある子どもを積極的に受け入れている学校は、まだ限られています。
それでも、そうした学校に限らず「わが子の特性に合う環境」を選ぶことで、安心して学校生活を送ることが可能です。
ここでは、発達特性ごとに相性が良いとされる学校タイプを紹介します。
2-1. 書字が苦手・処理速度がゆっくりな子
→ ICT化が進んでいる学校
・紙に書くことが負担になりやすい子には、タブレット学習との相性が良い場合があります。
・提出やノート整理もデジタルで完結できるため、負担を減らせます。
2-2. 提出物の管理が苦手な子
→ ICTが整備された学校
・アプリ上で提出状況や期限を確認できるので、子どもも保護者も管理しやすくなります。
→ 面倒見の良い学校
・提出物の一覧表を配布し、未提出の際は丁寧に声かけをしてくれる学校もあります。
2-3. スケジュール管理や自主学習が苦手な子
→ 学習サポートが充実した学校
・テスト前の計画立てを一緒に行ってくれたり、自習スペースを提供してくれるなど、学習面での伴走体制があります。
2-4. 空気が読めない・集団が苦手な子
→ 個性を尊重する校風の学校
・「そういう子もいるよね」と自然に受け入れられる雰囲気があります。
・「多様性」や「個性の尊重」を掲げる校風は、偏差値の高い学校に比較的多く見られます。
2-5. 得意分野が突出していて、普通の授業では退屈な子
→ 学力レベルの高い進学校
・授業レベルが高く、刺激のある学習環境が得られます。
・英検上位級や数学オリンピック出場者など、似た特性を持つ同級生と出会えることもあります。
✨ その他にも…
・対話型の授業
・実験や体験を重視した授業
など、私立中高一貫校にはさまざまな学びのスタイルがあります。お子さんの特性に合わせて柔軟に学校タイプを検討してみてください。
3. 学校選びに必要な情報を集める
地域の中高一貫校の情報を集めます。
HPや受験雑誌、掲示板にもさまざまな情報がありますし、在校生の保護者から直接聞くという手もあります。
ただ、発達凸凹のない子と特性のある子では、必要な情報が違うこともあります。
発達特性のある子のための情報は、どうやって集めるのが良いのでしょうか。
3-1. 医師や療育関係者から地域の学校情報を聞く
こんなとき、意外とおすすめなのは、児童精神科医の先生や、ベテランの療育の先生に相談してみること。
色々な凸凹さん達を長く担当してきて、どのような特性の子がどこの私立中学校に行き、どのように学校生活を送っていて…というデータを持っている専門家が結構います。
「この子に似た子が、そこの学校に行っていて…。」という話が聞けたら、ラッキーですね。
3-2. 塾講師から得られるリアルな評判
長年、地元で受験指導をしているような塾の先生なら、特性のある子の指導経験が豊富なはずです。
また、塾の先生は塾生の中学入学後の様子についてもよく知っているため、リアルな情報を得ることができます。
発達障害を持つ子に合う塾・経験のある塾講師の見つけ方はこちらの記事をどうぞ↓
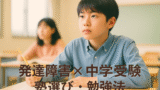
3-3. 学校見学・説明会は早めに参加する
中学受験の勉強を自発的に続けていくためには、本人が「この学校に合格したい」と思えることが大切です。
そのために効果的なのが、早めの学校見学です。
発達特性のあるお子さんは特に、早めに学校見学をすることをおすすめします。
イメージする力が弱いお子さんが多く、実際に学校を見ないと中学校生活を具体的に想像しにくいため、モチベーションが上がりにくい傾向があります。
早めに上級生の学校生活や授業・部活の様子を見て、「この学校に行きたい」という気持ちを持てると、勉強への意欲も高まりやすいです。
公立・私立を問わず、多くの学校で定員や予約が必要なので、早めの申し込みをおすすめします。
3-4. 出願書類・受験科目を確認する
受験を検討している学校の受験科目・出願に必要な書類を確認しましょう。
私立中学校では、以下のようにさまざまなパターンがあります。
・国・算・理・社の4科目
・通知表や調査書の提出
・作文や面接
・適性検査
・専願枠の有無
・英検など加点事項の有無
作文や面接など非常に苦手なことが含まれる場合は、その学校を回避し、得意なことで受験できる学校を選ぶという考え方もあります。
また、志望校間で受験科目が異なる場合、学習内容が増えるため注意が必要です。
たとえば、
- 第一志望が4科目
- 第二志望が2科目+適性試験
- 第三志望が2科目+作文・面接
という場合、4科目+適性+作文・面接すべてに対応する必要があります。
適性試験や作文・面接が得意、という場合はそのままで良いのですが、苦手で学習時間がかかりそうな場合は、志望校の優先順位を考えて、①受験校を変える
②作文や面接は最低限の勉強で…と割り切る
など工夫が必要です。
3-5. 通知表(調査書)の扱いと評価基準を知る
発達特性を持つお子さんの中には、学力のわりに通知表の評価が良くないケースもあります。
忘れ物や授業態度で評価が下がる場合など、出願時に調査書が必要な学校では不利になるのでは…と不安に感じる保護者の方もいるでしょう。
通知表や調査書は学校によって考慮する点や度合いが異なります。
「欠席数」や「所見」以外はほとんど見ない学校もあるため、心配な場合は説明会などで質問して確認しておくと安心です。
3-6. 支援級からの受験は通知表の扱いに注意
支援級在籍の場合、通知表は言葉での評価になり、通常学級のような段階別評価ではありません。
そのため、出願に調査書が必要な場合は、以下のような方法が考えられます。
・段階別評価がある通知表で評価しなおしてもらう
・通常学級に転籍する
自治体によっては、通知表を段階別評価に評価しなおしてくれるところもあるため、確認してみましょう。
ただし通常学級の基準で評価されるため、成績が低く出ることもあります。
このため、中学受験を見据えて高学年から通常学級に転籍するお子さんもいます。
その場合は、環境の変化による負担が大きくなるため、お子さんの様子をよく見ながら慎重に判断する必要があります。
いかがでしたか?
この記事が、お子さんに合った学校を選ぶ際の参考になれば嬉しいです。
中学受験に関する他の記事も、ぜひご覧ください。
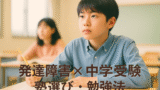

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


