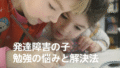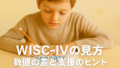<2025年7月更新>※本記事にはプロモーションを含む場合があります。
発達障害(自閉症スペクトラム・ADHD)やグレーゾーンのお子さんについて、
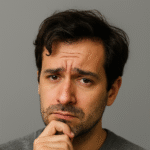
体の動きがぎこちなくて、運動が苦手みたい。

(球技、縄跳び、鉄棒など)極端にできない運動があって…。
こんなお悩みをお持ちの保護者の方はいらっしゃいませんか?
運動会や体育の授業で、運動に対して苦手意識を持ってしまうお子さんも少なくありません。
日常の中で、どうサポートすればいいのか悩んでいる方も多いのではと思います。
この記事では、以下のような内容について、保護者としての経験を交えてわかりやすくお伝えします。
- 発達障害のある子が運動を苦手とする理由
- 特性に配慮できる今注目の運動教室をご紹介
- 家庭でできる工夫と、サポートにおける注意点
自閉症スペクトラムとADHDの特性を持つ男子学生の母で、副業ライターをしています。
息子は現在、私立の中高一貫校に元気に通学中です。
幼少期はとても育てにくく、当時は情報も少なくて、子育てに不安を感じる毎日でした。
「私だったらこれが知りたかった。」という『痒い所に手が届く情報提供』を目指して、
同じように悩む保護者の方に向けてブログを更新中です。
息子のエピソードや、本当に役立った情報を保護者目線でご紹介していきます。
1. 発達障害を持つ子が運動音痴になる理由とは?
発達障害を持つ子が、体育の授業でつらい思いをしたり、運動嫌いになってしまうのは、どうしてなのでしょうか?
その背景には、発達性協調運動障害や集団行動の難しさなど、特性による困難さが関係していることがあります。
理由1 発達性協調運動障害による運動の難しさがある
発達性協調運動障害は、手先の不器用さや運動技能の弱さなどを特徴とする、発達障害の一種です。
ASDやADHD、LDなどの発達障害の子の中には、発達性協調運動障害を合併するケースが多いと言われています。
この障害を持つ子は、不器用さや運動技能のつたなさが、早期から極端に現れるのが特徴です。
「不器用」「運動音痴」に該当する人は多くいますが、その中でも「極端にできない」「日常生活に支障をきたしている」ような場合には、発達性協調運動障害に該当することがあります。
診断には専門医の判断が必要ですが、以下に具体例を挙げてみます。
<手先や動きの不器用さの例>
- 物をよく落とす
- 人や物によくぶつかる
- 練習してもちょうちょ結びができない
- 箸やペンの持ち方がぎこちない
- 字を丁寧に書けない
<運動技能のつたなさの例>
- 練習しても自転車に乗れない
- 走り方がぎこちなく速く走れない
- ダンスや体操が苦手
- チームプレイのスポーツが苦手
※これらの例に該当しても、必ずしも発達性協調運動障害にあたるとは限りません。
あくまで目安程度にご覧ください。診断には医師による評価が必要です。
また、靴ひもや箸、逆上がり、自転車などは、できるようになる時期に個人差があります。
単に時期が遅いだけで、この障害に該当するとは限らないことも付け加えておきます。
理由2 集団行動やチームプレイが苦手
発達障害のある子どもは、集団での行動やチームプレイに苦手意識を持つことがあります。
ASD傾向のある子は、他人の気持ちをくみ取ったり、周囲の動きに合わせたりすることが難しい場合があります。
ADHD傾向のある子は、集中が続かず、衝動的に動いてしまうため、集団の流れに乗れないことも。
その結果、周囲とうまくかみ合わず、誤解やトラブルにつながることも少なくありません。
ただ、チームスポーツは社会性や協調性を育む良い機会でもあります。
無理のない範囲で、楽しみながら参加できる環境があると理想的です。
2. 発達障害を持つ子も安心の体育・スポーツ教室紹介
発達特性から体育などで苦手な運動がある場合、学校やご家庭で対応できればいいですが、なかなか難しいこともあります。
そのようなお子さんにぴったりの、短期間から手軽に個別指導を受けられる教室をご紹介します。
マンツーマンで運動の困りごとを解決
体育・スポーツ家庭教師ファースト
鉄棒や縄跳び、マット運動など、学校体育でつまずきやすい種目に悩んでいませんか?
ファーストは発達障がいコースもある派遣型個別指導の体育・スポーツ教室です。
特性に理解のある指導者が、一人ひとりのペースに合わせてマンツーマンでサポートしてくれます。
(兄弟・友達同士でのグループレッスンも可。)
かけっこ・球技・水泳など幅広い学校体育にも対応。
近所の公園や広場など、お子さんがリラックスできる場所でレッスンを受けられます。
また、実際に担当するコーチで体験レッスンができるので、「相性が合うか不安…」という保護者の方にも安心です。
・鉄棒や縄跳びができないので、短期間でレッスンを受けたい。
・スイミングスクールの背泳ぎで、何か月も進級できない、指導してほしい。
・球技が苦手なので、友達との遊びや体育で困らないように教えてほしい。
✔ 学校体育で困りがちな種目に幅広く対応
✔ 月180分以上であれば短期レッスンも可能
✔ 発達特性に配慮した丁寧なマンツーマン指導
✔ 無料体験レッスンあり(※一部条件あり)
3. 運動が苦手な発達障害の子に家庭で出来るサポートとは?
運動を苦手とする発達障害の子に対して家庭でできるサポートには、どのようなことがあるのでしょうか?
家庭で取り組みやすいこと、私が実際に試して息子のためになったことに絞ってご紹介したいと思います。
学校との連携
運動が苦手な発達障害の子どもは、体育の授業で誤解されやすいことがあります。
「やる気がない」「ふざけている」と叱責されたり、同級生にからかわれることも少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐためには、事前に担任や体育の先生に特性を伝え、「まじめに努力してもできないことがある」「上下さかさまになるのが怖い」「強調運動(縄跳びやスキップなど手と足、目と手など別々に動く機能をまとめ動かす運動のこと)がどうしても難しい」など、あらかじめ理解してもらうことが大切です。
どのようにサポートするかは学校の先生の判断になりますが、主治医や療育の先生からのアドバイスなどを伝えると、学校側が対応しやすくなる場合もあります。
粗大運動で体幹を鍛える
体のバランス感覚を養うために、粗大運動を取り入れるのも効果的です。
トランポリンやボルダリング、バランスボール、平均台、ブランコ、スラックラインなどは遊び感覚で体幹を鍛えられます。
日常的な姿勢の安定や運動全般の基礎力アップにもつながるので、楽しめるものを少しずつ試してみるとよいですね。
好きな運動を何か見つける
「運動が得意かどうか」よりも、「楽しい」と思える活動を見つけることも大切です。
得意ではなくても、少しでも達成感を味わえる運動があれば、それが自信につながります。
水泳やダンス、ヨガ、散歩など、個人で取り組めるスポーツもおすすめです。
🏠 わが家の体験談
息子も運動は苦手な方ですが、水泳と長距離走だけは得意。
特に長距離走には自信があるようで、体育のマラソンでは、運動が得意な子たちを抑えて自分が上の順位に立つことができて、「自分の方ができるスポーツもあるんだ。」と自信がついたようです。
水泳は習っていたので、人並みには泳げます。
また、野球は小さなころから好きで、父親とキャッチボールをしていたので、キャッチボールができるは、彼にとって、とてもプラスだったように思います。
友達と公園で一緒に野球をして遊ぶことができました。
苦手の克服はほどほどに
無理に苦手を克服させようとすると、練習を重ねても人並み以上になることは少なく、かえって「できない」という意識を強めてしまうことがあります。
苦手なことばかりを突き付けられ、やってもやってもうまくいかない経験を繰り返すと、結果として自尊心が下がることもあります。
苦手な運動の成長を焦るより、得意な分野で成功体験を積ませる方が、将来的には役立つことが多いはずです。
家庭でのサポートは「克服」よりも「楽しむ」ことを優先し、子どもの強みを伸ばす視点を忘れないようにしたいものです。
「その子が『できるようになりたい』という気持ちがあれば全力でサポートしてほしいが、(逆上がりやスキップ、縄跳びなどは)『生きていく上でどうしても必要なことなのか』という視点でも考えてほしい。たとえうまくいかなくても、それまでの頑張りを評価したり、褒めたりしてあげてほしい」とも。同じDCDでも一人一人困りごとやその程度は異なるといい「子どもと向き合い、話し合いながら、本人が望むことを手助けするのが大切」
字が汚い、縄跳びできない「不器用」な子…実はDCD(発達性協調運動障害)かも 周囲の理解と支援が必要です
長田真由美(2023年9月5日付・12日付 東京新聞朝刊)
運動が苦手な子にとって、体育の授業や運動会は、楽しいどころかつらい経験になってしまうこともあります。
だからこそ、大切な自尊心を傷つけられたり、自信をなくしてしまうことがないよう、周囲の理解とサポートが欠かせません。
無理に克服を目指すのではなく、その子なりの「できた」「楽しい」を大切にしながら、前向きな気持ちを育てていけるといいですね。
できれば何か一つでも「これなら好き」と思える運動に出会い、心と体の健康維持にもつなげられると、子どもにとって大きな力になります。
家庭でできる小さなサポートが、きっと未来の自信につながっていきます。