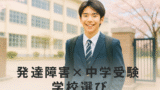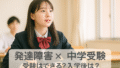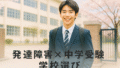<2025年9月更新>
この記事にはプロモーションを含みます
発達障害を持つお子さんの中学受験。
「塾はどんなところを選べばいいの?」
「勉強法は普通のやり方で通用するの?」
と不安に思う保護者の方は多いのではないでしょうか。
実際に、ADHDや自閉症スペクトラム(ASD)、グレーゾーンのお子さんは、塾の課題量をこなせなかったり、模試やテストで時間不足になったり、勉強計画を立てて進めることが苦手だったりと、受験勉強中も壁に直面しやすいものです。
この記事では、
発達障害の子の中学受験における
- 塾選びのポイント
- 勉強法でつまずきやすいこと
- 特性に合う受験スタイルや家庭教師の活用法
を、実体験を交えたブログ形式でわかりやすく紹介します。
同じ悩みを抱える保護者の方にとって、塾選びや勉強法を考えるヒントになれば幸いです。
ADHD+ASDの特性を持つ男子高生の母で兼業ライターです。
息子は中学受験の末、私立中高一貫校に元気に通っています。
息子に合う環境を求めて中学受験を始めてみると、発達障害を持つ子にとって必要な情報が極端に少ないことに気づきました。
発達障害を持つ子の中学受験情報を提供し、保護者の方を少しでも応援できればいいな…という思いで、本記事を書いています。家庭教師、塾講師経験があります。
<関連記事>中学受験だけでなく、英語力を伸ばすことも子どもの将来に役立ちます。
発達障害の子に合うオンライン英会話をランキング形式で紹介しています。
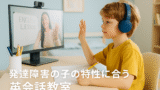
1. 発達障害の子が中学受験を選ぶ理由|体験ブログから見える背景
ここ数年、中学受験の受験者数は増加傾向にあり、少子化の中でも2025年は過去3番目に多い受験者数となりました。
そんな中、発達障害(ADHD・ASD)、グレーゾーンのお子さんが中学受験に挑戦するケースも確実に増えています。

どういう理由で発達障害を持つ子が中学受験をしているの?
発達障害を持つ子が、中学受験を選ぶ主な理由として、
- 子供の特性に合う中学校に通わせたい
- 高校受験では提出物や内申点で不利になりやすいため避けたい
- 学力や特性が似ている仲間に出会いやすい
- 小学校までの人間関係をリセットしたい
このような理由があるようです。
多様な教育方針や校風を持つ中高一貫校の中から、特性に合った学校を選べることや、高校受験にとらわれず自分の好きなことに打ち込めることは、発達障害の子どもにとって大きな魅力です。
そのため、発達障害があるからこそ「中学受験を選ぶ」というご家庭が増えているのは自然な流れだと言えるでしょう。
2. 発達障害の子が中学受験でつまずきやすいこと
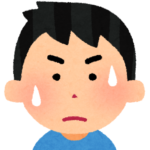
発達特性を持つ子が中学受験で困ることって、何なんだろう?
発達障害を持つ子どもが中学受験に挑戦する場合、メリットだけでなく特有の難しさもあります。
「なぜ勉強が進まないのか」「塾でうまくいかないのか」には共通する傾向があり、事前に理解しておくことでサポートしやすくなります。
- 集団塾が合わない場合がある
- 塾の課題がこなせない
- 模試・入試で時間不足になる
- ADHDの特性でミスを連発する
- 勉強計画を立てて進めることが苦手
2-1. 集団塾が合わない
発達特性によっては、大人数の一斉授業に適応しにくいことがあります。
- こだわりが発動して塾が指導する問題解法を受け入れられない
- 気が散りやすくて長時間の一斉授業に耐えられない
このような状況では、進度の速い集団塾で勉強の進行を乱すと叱られ、本人が辛くなってしまうことも少なくありません。
2-2. 塾の課題量をこなせない
処理速度が遅めの子、勉強に長く集中できない子に多い悩みです。
集団塾は、発達特性のない子でもこなせないほどの課題が出されることが多いので、場合によっては課題量を調整する必要があります。
2-3. 模試・入試で時間不足に
処理速度の遅さは、模試や入試本番で「最後まで解き終わらない」につながります。
テスト時間内に終了するよう、その子に合った「テストの受け方」の指導が必要な場合もあります。
2-4. ADHDの特性でミスを連発
特性のない子でもミスはでるものですが、ADHD傾向のある子は特に基本的なミスを連発してしまうことがあります。
どんなミスをするのか、その対処法も併せて、その子の特性に応じて分析・指導する必要があります。
2-5. 勉強計画を立てて進めることが苦手
スケジュールを考えて実行するのは、小学生にとって難しいものです。
特に発達特性を持つ子どもは、大人のサポートがなければ勉強計画を立てて実行することが難しいケースが多いです。
ちなみに…
我が家の息子は、1以外のすべてに当てはまっていました。
3. 発達障害の子に合う中学受験の塾選びと勉強法
発達障害の子どもの中学受験は、特性に合った勉強法や塾の選びがとても大切です。
大手の集団塾に通うのが合う子もいれば、家庭教師や配慮ある中小規模の塾の方が力を発揮できる子もいます。
3-1. 発達障害の子に合う中学受験の勉強法【特性別の選び方】
勉強が得意で、ご家庭で工夫をすれば集団塾でやっていけるタイプの子ならば、大手集団塾に所属し、周囲の受験生と切磋琢磨することが合格への近道です。
一方で、大手塾が難しい子の場合は、戦略的に「別の学習スタイル」を選ぶ必要があります。
- 可能であれば大きめの集団塾に通い、家庭でフォローする
- 大手塾が難しければ、中小規模の集団塾を検討する
- 集団塾が合わなければ、発達障害に理解のある家庭教師を利用する
3-2. 大手塾が合わない子におすすめの中小規模塾
大手集団塾で勉強することが難しいと、親御さんは「中学受験は難しいのかな?」と思われるかもしれません。
しかし、それは今の学習環境がお子さんに合っていないだけのこと。
お子さんに合った環境で勉強を続けることができれば、受験可能な子が実は多いのです。
大手塾が難しい場合でも、中学受験では「できれば集団塾に通う」ことが望ましいとされます。
その理由は以下の通りです。
- 合格までに必要なカリキュラムが整っている
- 周囲との競争効果でモチベーションが維持できる
- 様々な受験生のデータを持っているので、合格可能性の判断に役立つ
ただし、大手塾にこだわる必要はありません。
特性に配慮して指導してくれる中・小規模の集団塾の方がうまく受験生活を乗り切れる場合も多いです。
「子供の特性に合った環境」を求めて中学受験をされるのであれば、難関校にこだわらないというご家庭も多いのではないでしょうか。
いわゆる「ゆる受験」が良いと思われる方もいらっしゃるでしょう。
このようなご家庭にとって、特性に配慮してくれる中・小規模の集団塾は強い味方です。
<我が家の場合>
息子も、中規模の集団塾に通いました。
息子は4~5年生の頃、自分が良いと思う解法にこだわってしまったり、解法として指導されているのに本文にアンダーラインを引かなかったり…ということがありました。「先生が言っているから取り合えずやってみよう。」というのは通用しないタイプなのです。
そんな息子に対し、叱って無理に強制するのではなく、やる必要性を丁寧に説明したり、時には放っておいて「指導された方法でやらない不利益」を本人が実感したときに、改めて話してくれたり…本当に柔軟に対応してもらいました。
3-3. 発達障害の子に向いている塾の見つけ方
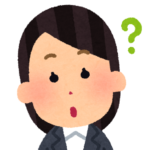
でも、特性に配慮してくれる塾って、どうやって見つけるの?
「発達障害の生徒も受け入れ可」と明記してあればわかりやすいですが、それ以外の塾でも、実は発達障害の子を受け入れる、指導のノウハウを持っている塾はたくさんあります。
以下の特徴がある塾は、発達障害を持つ子に向いている可能性があります。
- 習い事との両立など、様々なニーズを持った受験生が在籍している
- 合格実績だけがセールスポイントではない(難関校以外の受験生も尊重される)
- 1クラス当たりの人数が少ない
- 入塾の問い合わせに「授業を妨げることが無ければ受け入れる」など、条件付きでも受け入れを明言してくれる
- 講師が経験豊か(色々な子供に対応してきた経験がある)
上記はあくまで目安ですが、こうした特徴を持つ塾であれば、特性に合った受験生活を支えてもらいやすい傾向があります。
4. 家庭教師を活用した中学受験の勉強サポート方法
4-1. 保護者や家庭教師がフォローすべき学習サポート
中学受験は保護者のフォローが不可欠だと言われます。
スケジュール管理、教材の管理、送迎、体調管理など、子供だけでは難しい部分は、保護者の協力が必要です。
ただ、家庭でフォローすることはそれだけではありません。
次のようなことまで対応するのは難しいため、塾に加えて家庭教師という選択肢を検討するご家庭もあります。
- 模試やテスト結果を分析し、弱点を見つける
- 過去問の間違えた問題のうち、解けなければいけない問題と捨て問を選別する
- 間違えた問題を繰り返し解く、類題なども使ってスムーズに解けるまで定着させる
- 解いた過去問の時間配分を振り返り、本番での時間配分の作戦を考える。
これらは発達特性がなくても、小学生が一人でこなすのは難しく、発達障害を持つお子さんならなおさら、大人のサポートが欠かせません。
保護者にとっても、これをフォローするのは難易度が高くないですか?
ですが、受験勉強を経験した方なら、こうしたプロセスが合格に直結することは、おわかりいただけると思います。
4-2. 塾と家庭教師の併用でも費用を抑える戦略
家庭教師というと高額なイメージがありますが、工夫次第で費用を抑えることも可能です。
- 集団塾は「基本ペースメーカー」と割り切って追加の講座を取らない
- 個別対応が必要な部分は家庭教師に依頼する
- 比較的予算が抑えられるオンライン家庭教師を選ぶ
このように役割分担を明確にすると、経済的にも現実的な形で家庭教師を利用できます。
オンラインの家庭教師なら、ご自宅の場所は関係なく、発達障害の子の指導を得意とする講師を全国から探すことができるのも魅力です。
4-3. 発達障害に強いオンライン家庭教師おすすめ2社
自分にあった先生が選べる!【家庭教師のサクシード】
オンラインと対面指導の両方に対応しており、家庭の都合に合わせて選べます。
中学受験コースをはじめ、発達障害コース・不登校コースなど多彩なカリキュラムを用意。
登録講師は7万人以上で、プロ講師限定・女性講師限定・出身校指定など、希望に合わせて依頼できます。
講師は何度でも交代可能なので、「相性が合わないかも」と心配なお子さんでも安心です。
さらに、入会金・解約手数料・教材費はすべて無料。
学年が上がっても科目数が増えても追加料金はなく、1回の授業で複数科目を受講できます。コストを抑えつつ、安心して続けられる仕組みです。
👉 特性に合った指導を探している方は、まずは気になる講師の体験授業から始めてみてください。
★★★★★★★★★★★★
家庭教師ファースト
オンラインと派遣の両方に対応しており、派遣型は全国展開しています。
発達障害専門コースを設けているのも大きな特徴で、特性に配慮できる講師が指導します。
授業では宿題を1日分ずつ出し、生活リズムに合わせて「いつ・何を勉強すればよいか」を提案。勉強計画を立て、遂行するのが苦手なお子さんでも安心です。保護者へのヒアリングも丁寧に行われます。
さらに安心できるポイントは、体験授業を実際に担当講師が行うことです。
家庭教師派遣では本部スタッフが体験だけ担当するケースもありますが、これでは本当の相性は分かりません。実際の講師と体験できるので、始める前にしっかり見極められます。
👉 発達障害に強い講師を探している方は、まずは体験授業から試してみてください。
5.まとめ
発達障害を持つ子の中学受験では、集団塾が合わない、時間配分や課題量に苦労する、ミスを繰り返すなど、特有の悩みが出てきます。
だからこそ、お子さんの特性に合う塾を選ぶこと、そして保護者や家庭教師など周囲の大人が学習をフォローすることが、中学受験を成功させる大切なポイントになります。
この記事が、同じように悩む保護者の方にとって、塾選びや勉強法を考えるヒントになれば嬉しいです。
中学受験についてはこのような記事も書いています。
私立中学に入った後の実態を体験ブログとしてまとめました。

「発達障害 中学受験 学校選び」で検索される方も多いテーマです。
実際に体験した学校選びの悩みと解決のヒントをまとめました。