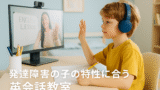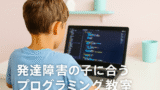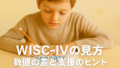<2025年9月更新>

モンテッソーリ教育って今話題の教育法みたいだけど、発達障害を持つ子にも効果があるの?
と気になっている保護者の方はいませんか?
実はモンテッソーリ教育は、もともと障害児教育を土台として発展してきた歴史があります。そのため、発達に特性のある子どもとも親和性が高いと言われています。
私自身も幼少期にモンテッソーリ教育を実践する幼稚園に通っていました。
当時、その園には障害を持つ子どもたちが多く在籍していて、一人ひとりが自分のペースで学んでいたのをよく覚えています。
そして、私の子供たちが通ったのもまた、モンテッソーリの幼稚園。
特に発達障害のある息子には、モンテッソーリ教育がとても合っていたと感じます。
こうした経験を踏まえて、今回は
なぜモンテッソーリ教育が発達障害の子どもと相性が良いのか
について、6つの理由を中心にご紹介します。
1.敏感期を尊重した学びができる
モンテッソーリ教育の考え方は、「子どもは自分を成長させる力を持っている」という「自己教育力」を前提にしています。
子どもの自由な選択を尊重し、大人は環境を整えて援助することが基本にあります。
子どもは自らのうちに自分を成長させる力をもっています。子どもの自発的な活動ができるように環境を整えて大人は子どもの自由を保障し援助します。
モンテッソーリ教育|広島文教大学附属幼稚園
モンテッソーリ教育の大きな特徴のひとつに「敏感期」という考え方があります。
敏感期とは、子どもが特定のことに強い興味を示し、自然と集中して取り組むことができる発達の時期を指します。
例えば、秩序にこだわる時期、言葉を覚える時期、数や文字に惹かれる時期などがあり、この時期に合った学びは驚くほど身につきやすいと言われています。
発達障害のある子どもは「自分の興味があることには強く集中するが、それ以外はなかなか手をつけない」という特性を持つことが少なくありません。
モンテッソーリ教育では、まさにその「興味」や「敏感期」を尊重して環境を整えるため、特性を持つ子どもが無理なく力を伸ばしやすいのです。
✏️ 息子の場合
モンテッソーリ教育の幼稚園に通っていた私の息子は、発達障害の特性を持ちながらも、興味を持った教具に驚くほど集中していました。
特に文字や地図、数字などに夢中になり、ものすごい勢いで基礎から発展的な内容までマスターしていく姿が印象的でした。
これはまさに「敏感期」と「興味の力」が重なった瞬間であり、特性のある子どもが力を発揮できるモンテッソーリ教育の魅力を実感した経験です。
🔗関連記事🔗
「発達障害の子におすすめの習い事5選」もあわせてご覧ください。
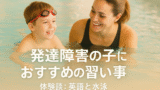
2.一斉活動が少なく、自分のペースで進められる
多くの幼稚園や学校では、先生の指示に従ってみんなで同じ活動を一斉に行うことが一般的です。
しかし発達障害のある子どもの中には、集団での一斉行動が苦手だったり、自分のペースを乱されると不安やストレスを感じたりするケースが少なくありません。
その点、モンテッソーリ教育では「自由選択活動」が中心に据えられており、子どもは用意された教具の中から自分のやりたいものを選び、集中して取り組むことができます。
先生は一方的に全員を同じ方向に導くのではなく、子ども一人ひとりを観察しながら必要なときにそっと手助けをする役割を担います。
✏️ 息子の場合
幼稚園時代には「みんなと一緒に同じことをする」活動よりも、自分で選んだ教具に取り組んでいるときの方がずっと落ち着いていました。
自分の興味に没頭できる時間が保障されていたからこそ、周りに合わせる ことが難しい特性を持ちながらも、安心して園生活を送ることができたのだと思います。
🔗関連記事🔗
発達特性を持つ子の中学受験の塾選びに役立つ情報も紹介しています。
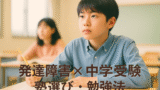
3.異年齢のクラス編成で育ち合える
モンテッソーリ教育の大きな特徴のひとつに、年齢の異なる子どもたちが同じクラスで学ぶ「縦割り保育」があります。
通常の園や学校では、同じ学年の子どもだけで構成されることが多いのに対し、モンテッソーリでは3学年ほどが一緒になって活動を行います。
この仕組みは、発達に凸凹のある子どもにとって大きなメリットになります。同年齢の中だけで比べられると「できる・できない」が際立ってしまい、自己肯定感を下げてしまうこともありますが、異年齢の中にいると自然に役割や居場所を見つけやすいのです。
年上の子は年下に教えることで自信を深め、年下の子は年上の姿を見て刺激を受けるといった、相互の育ち合いが生まれます。
✏️ 息子の場合
息子も、同じ年齢の子と比べれば「ずっとできないこと」や「逆にずっと得意なこと」がありましたが、年齢が入り混じったクラスの中では、それが自然な個性として受け入れられていました。
凸凹を抱えた子どもにとって、異年齢で過ごす環境は、比べられる不安をやわらげ、自分らしさを大切にしながら成長できる場になっていたと感じています。
🔗関連記事🔗
ギフテッド2Eの子の特徴やリアルな姿についてまとめました
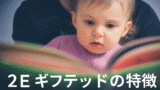
4.感覚教具で理解を深められる
モンテッソーリ教育では、子どもが五感を使って学べるように「感覚教具」が数多く用意されています。
ピンクタワーや色板、音の違いを比べるベルなど、形・色・大きさ・重さといった感覚に直接働きかける教具が代表的です。これらは一見「遊び」のように見えますが、実際には子どもが抽象的な概念を具体的に理解する手助けをしてくれます。
発達障害のある子どもの中には、言葉だけの説明では理解しにくい、数や空間認識といった抽象的な内容をイメージしづらいといった特性を持つ場合があります。
感覚教具を使うことで「実際に触れる」「見比べる」「繰り返し試す」といった体験を通じて、頭の中だけでは難しい理解を、体感として積み重ねていくことができるのです。
✏️ 息子の場合
息子も幼稚園時代に、数字や地図に関連する教具に強い興味を示しました。
具体的な形や視覚的な工夫があったおかげで、ただ暗記するのではなく「実際にわかる」という感覚を持てたように思います。
数を学ぶときも、まずは丸いビーズのような玉が「1」。それが10個連なって棒状になり「10」になる。さらに棒状の10が10個集まって正方形の板になり「100」。その板が10枚集まって立方体の塊となり「1000」を表す――このように、実際の分量を目で見て手で触れることで数を理解していきました。
教具に夢中になって繰り返すうちに、自然と基礎から発展的な内容へと進んでいった姿は、まさにモンテッソーリならではの学びの力を示していました。
🔗関連記事🔗
発達特性が武器になる?英語学習についてまとめました
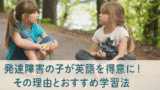
5.秩序ある環境が落ち着きを育む
モンテッソーリ教育では、環境の整え方をとても大切にしています。
教具はそれぞれ決まった場所に置かれ、使ったら必ず元の場所に戻すことが基本です。
部屋の中は整然としていて、子どもたちが迷わず自分で選び、安心して活動できるように工夫されています。
発達障害のある子どもの中には、見通しが立たない状況や環境の乱れに強い不安を感じる子もいます。また、注意が散りやすく集中が途切れやすい特性を持つ子にとっても、秩序立った空間は余計な刺激を減らし、集中を助ける役割を果たします。
✏️ 息子の場合
息子も、幼稚園で「いつもの場所にいつもの教具がある」という安心感の中で落ち着いて過ごしていました。
片付けや順番を守るといったルールは最初こそ難しかったのですが、環境全体が秩序立っていることで自然に身につき、家庭でも同じ習慣が生きてきたように思います。
整った環境に支えられて、安心して学びに向かえることは、モンテッソーリ教育の大きな魅力のひとつです。
6.自立と生活スキルを大切にする
モンテッソーリ教育では、文字や数の学習だけでなく、日常生活に直結する「生活の練習」が重視されます。
靴をそろえる、服をたたむ、水を注ぐ、植物に水をやるといった一見ささいに思える活動も、教具と同じくらい大切な学びの時間とされています。
発達障害のある子どもは、手先の不器用さや段取りの難しさなどから、日常生活のスキルでつまずきやすいことがあります。
モンテッソーリ教育では、そうした活動を「練習の機会」として用意してくれるため、失敗を繰り返しながらも自分の力でできるようになる体験を積むことができます。これは「できた!」という成功体験を増やし、自己肯定感を高める大きなきっかけになります。
✏️ 息子の場合
息子も幼稚園での生活の練習を通して、少しずつ自分でできることが増えていきました。
モンテッソーリ教育では、身支度の方法を目の前で実践してくれますし、物の置き場所もわかりやすいため、特性を持つ子どもでも取り組みやすい環境が整っています。
先生が黙ってゆっくりと雑巾絞りの手本を示す場面(この「見せ方」にも独自のノウハウがあります)を、息子が真剣な表情で見つめていたことを今でも鮮明に覚えています。
特に、最初は難しかった片付けや身支度ができるようになったことで、息子は「自分でできた」という成功体験を重ねることができました。
生活スキルを学びながら自信を育てられる点は、発達障害のある子どもにとってモンテッソーリ教育が持つ大きな強みだと感じます。
7.まとめ
モンテッソーリ教育は、もともと障害児教育を出発点として生まれた背景を持っています。そのため、発達障害の特性を持つ子どもにとっても親和性が高く、安心して力を伸ばせる環境を提供してくれます。
今回ご紹介したように、
- 敏感期を尊重した学び
- 一斉活動が少なく自分のペースで進められる仕組み
- 異年齢のクラス編成
- 感覚教具を通じた理解
- 秩序ある環境づくり
- 生活スキルを大切にする姿勢
これらはいずれも、発達に凸凹のある子どもが「自分らしく学べる」ために大きな助けとなります。
私自身や息子の経験を通しても、モンテッソーリ教育は「できないこと」に目を向けるのではなく、「今その子ができること・興味を持っていること」に光を当ててくれる学びだと実感しています。
特性を持つ子の成長を支えるひとつの選択肢として、モンテッソーリ教育を知っておくことは、保護者にとって大きな意味があるのではないでしょうか。
いかがでしたか?
この記事が読者の皆様のお役に立つことがあれば、私もとても幸せです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
🔗関連記事🔗