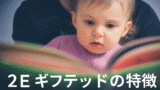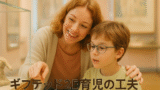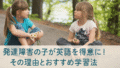<2025年10月更新>
本ページはプロモーションを含みます。
発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム)やグレーゾーンのお子さんに、
何か夢中になれる習い事を――。

ピアノは特性があっても続けられる?

どんな効果があるの?
そんな疑問に、わが家の体験を交えてお答えします。
✏️この記事でわかること✏️
・発達障害の子にピアノをすすめる理由
・ピアノを習って実際に感じた変化
・気軽に始められる教室の紹介
教室側ではない、保護者側からの視点で、ピアノについてご紹介していきます。
この記事を書いているのは、ASD・ADHDの特性を持つ男子高校生の母で、兼業ライターのさとです。 息子は今、私立の中高一貫校に楽しく通っています。
小さいころからピアノ・音楽教室・ドラム・プログラミング・英会話・スイミング・運動教室・塾など、本当にいろいろな習い事をしてきました。
息子が幼かったころは、発達障害を持つ子の子育て情報を探すのにとても苦労しました。
あの頃の自分と同じように悩む保護者の方に、「知りたかった!」と思ってもらえる情報を、体験を交えながらお届けできればと思っています。
🎈関連記事🎈
発達障害の子に英語がおすすめな理由と教室紹介
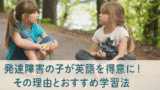
1. 発達障害を持つ子がピアノで得られるよい効果
発達特性の有無に関わらず、一般的に子どもの発育にとても良いとされるピアノ。
発達障害を持つ子どもの習い事としても非常におすすめです!
おすすめする理由を、脳科学の専門家の見解から我が家の息子の個人的変化まで、色々な観点からご紹介します。
・小さな「できた」成功体験の積み重ねが自己効力感を育てる
・レッスンを受けるだけでも脳の様々な部位を鍛え、活性化
・発表会は人前での自己表現と感情コントロールの練習になる
・音楽は仲間づくりのきっかけにもなる
1-1. 「できた!」が自信に!わが家の体験談から
「最初は難しいと感じた曲でも、練習を重ねると弾けるようになる」
という達成感を経験できるのが、ピアノの良さ。
実際、わが家の息子も「できた!」を重ねるたびに少しずつ自信がつきました。弾けなかったフレーズが弾けるようになる。その小さな前進が、次の挑戦を後押しします。
発達特性のある子どもは、「自分はやればできる」という感覚(=自己効力感)が育ちにくい、と言われます。叱られやすさや凸凹ゆえに、努力しても報われにくい体験が積み重なりやすいからです。
だからこそ、自己効力感アップに非常に有効なのは、小さな成功体験を積み重ねること。
音楽を通して「やればできる」という成功体験を幼少期から積み上げることができたら…、お子さんの成長を後押ししてくれる大きな財産になります。
わが家でも、難しい曲に出会ってイライラしても、「練習すれば弾けるようになる」という手応えが支えになりました。完璧主義が少しゆるみ、「まずはやってみる」が増えたのは、大きな変化でした。
1-2. 脳の発達・身体のバランスを育む
【1】脳のさまざまな部位に良い影響
脳科学者・瀧靖之先生(東北大学加齢医学研究所教授)によると、ピアノの練習は脳の「可塑性(変化する力)」を高め、脳梁や海馬など複数の脳領域のネットワークと体積を発達させることが分かっています。
さらに、その効果は指の動きといった限定的な能力だけにとどまらず、言語・空間認知・記憶・思考力など幅広い能力の向上につながる「汎化」が起こるのが特徴です。
(出典:研究ピアノ「ピアノが起こす脳の変化」シリーズ 2020年2月/瀧靖之)
https://research.piano.or.jp/series/piano_happen/brain/2020/02/taki09.html
【2】脳と身体の連動を強化
ピアノは「譜読み → 理解 → 両手の運動 → 聴覚で確認」のプロセスを何度も繰り返すため、脳の色々な部分を鍛え、連携を強めて脳全体を活性化させます。
結果として、広い脳領域をバランスよく刺激できる習い事です。
【3】練習嫌いでも恩恵あり
ピアノから受ける恩恵は、週1回のレッスンをするだけでも受けることができます。
毎日長時間の練習が難しいお子さんでも、楽しく続けるだけで十分な刺激が得られます。
1-3. 発表会の経験が人前での自信につながる
人前で演奏する経験を積むことで、自分を表現することに慣れていきます。
発表会では緊張の中で演奏をするため、自分の感情をコントロールする練習にもなります。
「思ったより本番に強い」「ある程度緊張してもできる」という自己理解にもつながります。
また、本番に向けて練習を重ねる中で、
「直前はあまり詰め込みすぎない方がいい」
「今回はもっと早くから練習しておけばよかった」
といった、目標に向かって努力する過程の学びも得られます。
🏠我が家の体験談🏠
普段はあまり練習をしない息子も、発表会では意外とうまくいくことが多いです。
ただし直前はナーバスになって荒れることも…。
それも含めて貴重な経験になっています。
繰り返すうちに、
「俺は本番には強い」
「大事な場面の前には緊張するけど、始まれば意外と大丈夫」
と、自分の強みに気づけるようになりました。
1-4. 音楽が「仲間とのつながり」を生む
これは、私の個人的な意見になりますが……。
私が大学時代に所属していた音楽サークルの仲間は、今振り返るとかなり個性的な人が多かったです。
その中には、発達特性を持っていた人もいたのではないかと思います(あくまで素人の感想であり、実際に確認したわけではありません)。
一緒にバンドを組んで演奏したり、好きな音楽の話をすることで、コミュニケーションが得意ではない人も自然に仲間の輪に溶け込んでいた印象があります。
音楽という共通の趣味を持つ仲間は、年齢や職業に関係なく、長く付き合っていけるのが魅力です。
2. 発達障害を持つ子におすすめのピアノ教室
2-1. 気軽に始められる楽器プレゼントの教室
楽器がもらえる音楽教室【EYS-Kids 子供向け音楽教室】全国各地にスタジオを展開している個人レッスン中心の音楽教室です。
特徴は、全47種類の中から好きな楽器を無料でもらえる点。楽器を買う必要がなく、最短2週間で用意してもらえるので初期費用を抑えて始められます。
月2回(30分)の個人レッスンが月々7,740円〜と料金も手頃です。
「まずは試してみたい」という方にもおすすめです。
無料体験はこちらから受けられます↓
2-2. 通学・オンラインどちらも可能な教室
椿音楽教室
↑関東・関西で200か所以上の教室を展開しています。
音楽教室には珍しくオンラインでの受講も可能。オンラインが選べると、慣れない場所が苦手なお子さんも安心ですね。送迎の負担からも解放されます。
11種類の音楽教室を開講しており、様々な楽器に対応しています。
60分の無料体験レッスンはこちらから↓
いかがでしたか?
ピアノは、脳の発達や自己効力感アップなど多くの効果が期待できる習い事です。
教室の形も多様になっているので、お子さんに合うスタイルを見つけて、楽しく続けていけるといいですね。
他の習い事についてはこちらもどうぞ↓
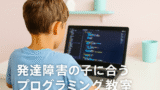
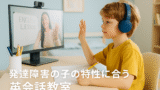
関連記事
勉強法や中学受験についても記事を書いています↓
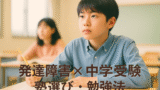

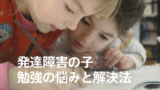
ギフテッドや2Eについて、特徴や子育てのコツを整理しました↓