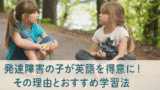<2025年5月更新>
この記事はプロモーションを含みます
発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム)、グレーゾーンのお子さんについて、保護者の方から

将来、子供がどうなるのか不安…
というお声をよく聞きます。
幼少期の凸凹ちゃんは日々の育児がとても大変。
育児で辛い思いをすることもある中、先の見えない不安を抱えていませんか?
実は私も、息子の幼少期は「将来に対する不安」に押しつぶされそうになりながら育児をしていました。
ですが、ある情報を得ることができるようになった頃から、将来に対する不安はほとんどなくなりました。
この記事をとお読みいただくと
について知ることができます。
この記事を書いている私さとは、ASD+ADHDの特性を持った男子学生の母で兼業ライターです。
息子の幼少期は育児が大変で、私自身も病気になり、将来が不安で辛かったです。
今はユニークな息子と毎日を楽しみながら穏やかに過ごしています。私たちについて詳しくはプロフィールをご覧ください。
不安の正体を知る
あなたがお子さんについて、「将来が不安」だと感じるとき、具体的には何について不安なのでしょうか?
例を挙げてみます。
この中に、あなたの不安に当てはまるものがありますか?
不安が大きいときには、「何が不安なのか」書き出すことが有効だと言われます。
不安を書き出すことが良いとされる理由について
「1 つは今抱えている悩みと距離をとって、客観的に見られるようになること。その結果、あせりがやわらぐので、落ち着いて物事を考えることができるようになります。もう 1 つは、それまで思いつかなかった選択肢に、自分で気づけるようになること。これは、書いた文章を読み直すことで得られる効果です。」
出典 厚生労働省 こころの情報サイト https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/docs/book_P9-14.pdf
漠然と…ではなく、何に対して不安を感じているのかを明確にできると、一歩前進。
その上で、なぜそんなに不安になるのか、原因を考えます。
不安になる原因は、わが子の「将来像」が見えないから
発達特性を持つお子さんは、社会では圧倒的に少数派です。
元々数が少ないうえ、発達障害を持つ子でもその特性は様々。
同じ発達障害を持つ子でも、特性や困っていることは全く異なります。
それゆえ、お子さんと同じタイプの「少し年上の子供」や「大人になった当事者」が周囲にはおらず、参考にできる未来のイメージが得られないのです。
<不安の原因>
子供がどのように成長していくのか、将来の姿がわからない。
不安の元凶はここにあります。
それならば…
お子さんの将来像を大まかにでも知ることができれば、その不安の大部分が解消されるはずです。
何か困ることが予想される場合には、それを避ける方法を模索したり、起こってしまった場合の対処法・相談先を用意しておくこともできます。
お子さんの将来が不安ならば、将来像を予測できるような情報を積極的に取りに行くことを考えましょう。
不安を解消し、穏やかな気持ちで子育てができるようになるといいですね。
わが子の将来像を知る方法
わが子が将来どのようになっていくのか。
何が強みになり、何に困るのか。
その大きなヒントとなる情報をどうすれば得ることができるのか、ご紹介します。
将来像を知る方法① 専門家に聞く
●小児科医・児童精神科医
発達障害に詳しい小児科医、児童精神科医は、色々な年齢の発達障害の特性を持つ子供を数多く診ています。
「早くから診断がついてしまうことが怖い」という保護者の方の声を聞きますが、診断を付けないよう希望して受信できる場合もあります。
(幼いうちは診断名を付けない方針の専門医もいます。)
育児をしていて不安や困っていることがある場合は、診断の有無にかかわらず医師に相談することが可能です。
あまり頻繁に相談できないのが難点ですが、今の困りごとはもちろん、将来の不安についても相談してみると、将来像につながる助言がもらえるかもしれません。
●ベテランの療育の先生
長年にわたって発達障害を持つ子供に接し「こういう子は将来こうなる」という経験の蓄積があるベテランの療育の先生なら、「この子は、中学生頃にこういう課題が出てくる。」「就職するころには…」と、大体の予測ができる方が多いです。
ただ、療育はここ10年くらいの間に新規参入した施設も多く、比較的経験の浅い先生が多いのが実情です。若手の先生は小さな子供に対する対応は熟知されていても、一人の子供の成長を長年見守ってきたわけではないので、将来像まではわからない先生も多いです。
ベテランの先生を見つけること自体が難しい場合もあります。
療育施設を探す際、先々の助言が欲しい方は先生の経験値も判断の基準に加えても良いですね。
<我が家の場合>
ずっとお世話になっている療育の先生は、まるで預言者のよう。
「3、4年生頃には多動が落ち着く。」「中高生の間は、親友はできないかも。学生生活を本当に楽しめるようになるのは、大学生くらいかな。」「〇〇が得意になるでしょうね。」など、将来のことについて、「予言」が外れたことはほとんどありません…。
「大学生くらいになると、だいたいこんな感じの子になる。」という療育の先生の語る将来像に、息子は見事に近づいています(笑)。
ただ、あまり積極的に口を出しすぎると、本人や親の価値観を壊してしまうと考えていらっしゃるのだと思いますが、あまり積極的に「○○をした方が良い。」とは言いません。
ですが、大事な進路選択の際には、こちらから相談すると方向性を示してくれる心強い味方です。
将来像を知る方法② 検査を受ける
検査の目的は、
子どもの得意なことと苦手なことを把握し、子どもに合った関わり方や、伸ばすと良いポイントを知る
ことです。
発達検査や知能検査の結果からは、得意・不得意を知ることができ、園や学校でどんなことに困る可能性があるか、どのようなことが向いているかについて予想することができます。
知能検査や発達検査の代表的なものについて、以下に簡単にまとめました。
●「知能検査」と「発達検査」
発達が気になる子供たちが受ける心理検査としては、WISCなどの「知能検査」と新版K式などの「発達検査」があります。
発達検査と知能検査の間には、厳密な区別があるわけではありません。
知能検査で測定する対象は「知的能力の発達や状態」で、発達検査では、「知的発達も含む、より幅広い領域の精神発達の状態」が対象となる場合が多いようです。
代表的な2つの検査についてご紹介します。
●新型K式発達検査
0歳~成人まで幅広い年齢層で行うことができる発達検査で、認知機能の評価以外にも姿勢・運動の発達や言語・社会性の発達など幅広い領域にわたって評価する検査です。
乳児期の子どもや運動発達の遅れや重度の知的障害のある子どもにも行うことができます。
「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会」の3つの領域における発達の状態を測定し、「発達年齢(DA)」と「発達指数(DQ)」を算出します。
発達年齢は、「発達が何歳相当か」ということを示す指標です。
発達指数は、「発達年齢÷本人の実際の年齢(生活年齢)x100」という計算式で算出されます。発達年齢が生活年齢と同じ場合は、「DQ=100」となります。
●WISC-Ⅳ
WISC-Ⅴが一番新しい検査ですが、現在日本で一番普及して使用されているのはWISC-Ⅳですので、この記事ではWISC-Ⅳを中心にご紹介します。
WISC-Ⅳでは、全体的な認知能力を表す全検査IQと「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」の4つの指標をそれぞれ数値化した結果を得られます。
WISCはウェクスラー式知能検査の1つですが、この知能検査は年齢に応じて、幼児期のWPPSI(WPPSI-ⅢⅣは2歳6ヵ月~7歳3ヵ月)、児童期のWISC(WISC‐Ⅳは5歳0ヶ月〜16歳11ヶ月)、成人期のWAIS(WAIS-Ⅳは16歳0ヵ月~90歳11ヵ月)があります。
WISCの数値からどのようなことがわかるのか、WISCの見方や疑問点をこちらの記事にまとめました↓
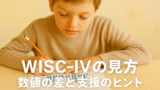
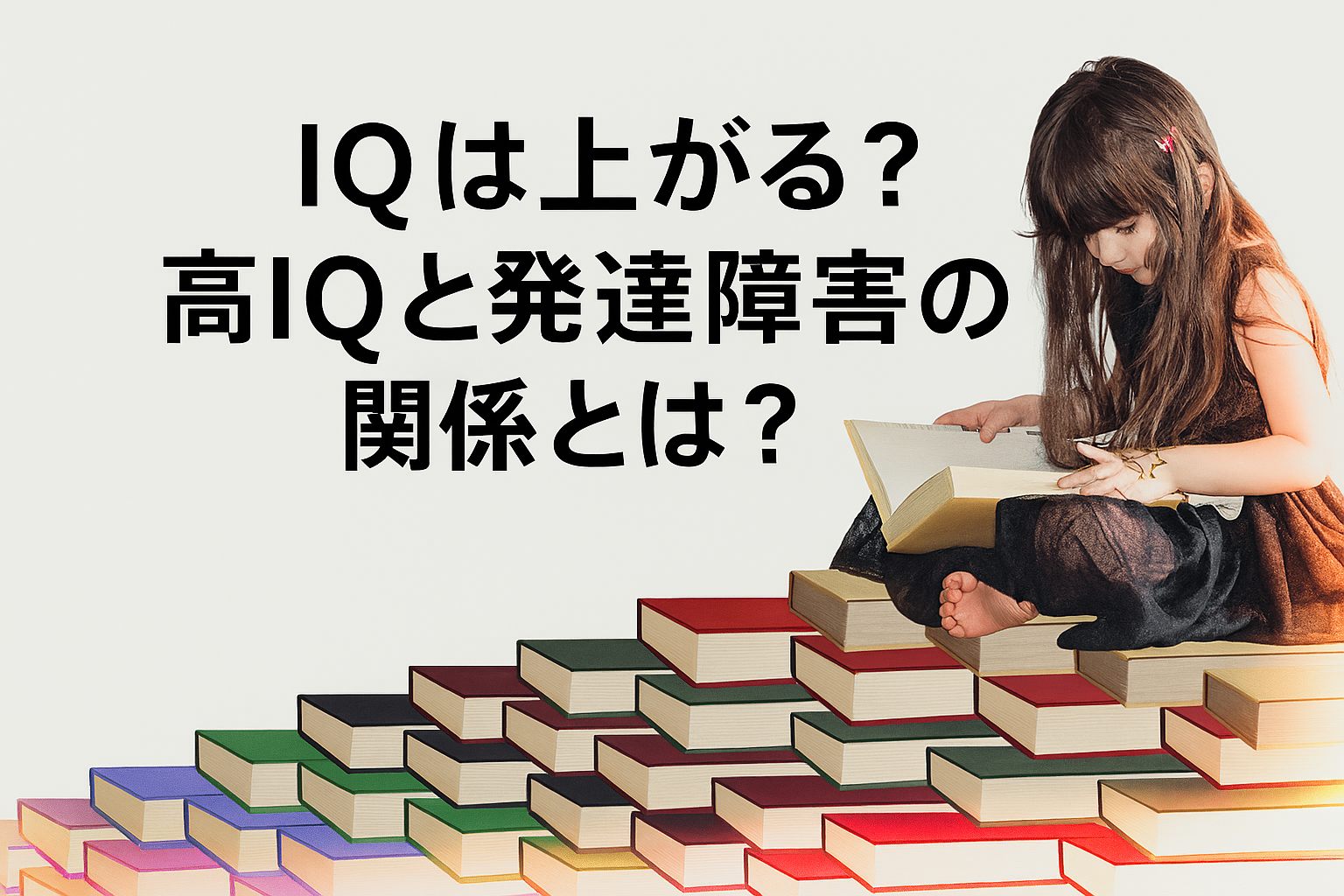
将来像を知る方法③ 似た先輩を探す
●似た特性を持つ、年上の人を探してみる
将来像を知るために、子供と似た特性を持つ、少し年上の子や大人を見つける、という方法もあります。
もちろん、全く同じ人間はいませんから、似た特性の人だと思っても、全く違う成長を遂げる可能性があります。
環境による変化、不測の事態によって、育ちが大きな影響をうけてしまうことも考えられます。
ただ、この「将来像」を見つけられた方が、避けた方が良いこともわかってくるので、その「不測の変化」を避けられる可能性が高まります。
●親の会・当事者の会
自治体が主催するものや大学などの教育機関、民間企業や個人によるものなど、様々な親の会や当事者の会が行われています。
<我が家の場合>
私は「息子と似た特性の先輩」を求めて、親の会に数回参加したことがあります。
しかし、その会で一度にお会いできるのは数十人。
息子より年下の子の親御さんも多く、息子と似たタイプの年上の子の親御さんには、結局出会えませんでした。
親の会自体は、悩みを共有したり、心置きなく話ができるので、有意義な時間を過ごせたのですが、「息子と似た特性の先輩」の親御さんには巡り合えず、参加の目的は達成できませんでした。
最近ではは、オンラインの親の会や当事者の会もありますね。
オンラインであれば、わざわざ出向いて行ったのに空振り…というときも負担が少ないです。
住む場所関係なく探すことができるので範囲が広くなり、以前より将来のモデルとなる人が探しやすいという利点もあります。
将来像を知る方法④ 調べる
●本で調べる
 | アスペルガー症候群のある子どものための新キャリア教育 小・中学生のいま、家庭と学校でできること [ 本田 秀夫 ] 価格:2090円 |
↑「アスペルガー症候群のある子どものための新キャリア教育」 本田秀夫 日戸由刈 編著
 | アスペルガー症候群のある子どものための新キャリア教育【電子書籍】 価格:2090円 |
↑電子書籍版
3人の発達障害を持った青年の、幼児から社会人になるまでの育ちが細かく記録されており、進学・就職の節目で本人がどのように考えて何を選択したか、保護者がどのように関わったかがよく分かる一冊です。
それぞれの場面で、どのようなかかわり方をすればよいか…という本はたくさんあるのですが、
「こういう特性の子に、このような親の関わり方を続けると、将来どうなるのか」
を知ることができる本は、なかなかありません。
将来、社会生活を安心して過ごすためには、保護者がどのような関わりをすべきなのか、小さな頃から大人になるまで書かれており、何度読んでも気づきを得ることができます。
3人それぞれ、色々なことがあるのですが、「色々あっても、それでいいんだな。」と思わせてくれる一冊です。
●ブログ・SNSで調べる
発達特性を持つ中高生や大学生、社会人の親御さんのブログ・SNSの中から、ご自分のお子さんに似たタイプの人を探してみましょう。
「大きくなってどんな生活を送っているか」、「何に困っているか」を知る手掛かりになります。
困っていることの方が発信しやすく、上手くいっていることや楽しめていることの発信は少ない傾向にあるので、読んでいてあまり悲観的にならないように気を付けてくださいね。
手前味噌ですが、当ブログでは息子の成長の様子を「幼児期から中高生」でまとめてご紹介する記事を書いています。
↓こちらの記事では、4つの困った行動(「やめてが聞けない」「外出先で切り替えができない」「集団活動が苦手」「挨拶ができない」)が、成長と共にどのように変化したかをご紹介しています↓

Xでは、固定ページで息子の大まかな育ちについてご紹介しています。
(下の投稿は中学生当時のもの)
【おまけ】発達障害と犯罪について
最後に、発達特性を持ったわが子に他害や問題行動がある場合、まだ幼いうちから「将来犯罪者になったらどうしよう」と心配される方がいらっしゃるので、おまけとしてこの章を作りました。
凶悪犯罪が発生して、「犯人には発達障害があり…」という報道を耳にすると、「わが子が犯罪者になったらどうしよう…」と不安になっていませんか?
「発達障害を持っている」という共通点だけで、小さな凸凹ちゃんの親御さんが「自分の子供もこのようになったらどうしよう…」と不安になるのは、完全に取り越し苦労です。
犯人がどのような特性で、どんな環境で育ったのかわからず、お子さんと共通点があるかもわからないはず。
ご心配な方は、以下3つの抜粋を是非読んでみてください。
東京少年鑑別所で勤務していた時に調査したところ、少年鑑別所入所少年の中で発達障害を持つ例が占める割合は、可能性がある少年を含めても5%程度でした。つまり文部科学省の一般的なデータと同じ、むしろ少ないということがわかりました。非行少年には発達障害を持つ子が多いわけではないのです。(中略)
鑑別所で少年たちに対応していると、発達障害であることに加えて、その特性を周囲にわかってもらえないことや、親から虐待を受けていることが非行と関係しているのではないかと感じられることがありました。そこで、発達障害を持つ非行少年の既往歴を調べてみたところ、発達障害を持つ少年は、そうでない少年よりも「逆境的経験」、なかでも「心理的虐待」が多いという結果が得られました。心理的虐待とは子どもを必要以上に叱責したり子どもに対して暴言をはいたりすること、子どもが褒めてほしいときに褒めない、蔑む・からかうことなどをさします。
出典 発達障害の子どもは非行に走りやすいのか?_塩川 宏郷 | coFFee doctors – 記事
2000年 愛知県豊川市 17歳男子高校生による主婦殺人事件
2003年 長崎県長崎市 男子中学生による男児誘拐殺人事件
2004年 北海道石狩市 男子高校生による同級生母親殺人事件
2014年 愛知県名古屋市 女子高校(大学)生による毒殺(タリウム)未遂事件
これらの事件は、「広汎性発達障害」「アスペルガー症候群(現在の用語でASD)」とする鑑定結果が公表されている。しかしこれらの結果から「自閉症など発達障害が事件を引き起こす」と考えるのは、誤りである。発達障害と犯罪について発達障害そのものではなく、「二次障害」が、非行や犯罪のような行動化に深く関わっている。
出典 発達障害の「二次障害」と犯罪(西多昌規) – エキスパート – Yahoo!ニュース
発達障害のある人は犯罪の加害者になりやすいという傾向はありません。加害者ではなく,圧倒的に犯罪被害者となることが多いと言われています。重大犯罪に関する新聞報道などでは,加害者の精神鑑定の結果,発達障害の診断名が記事に載ることで,「発達障害のある人は犯罪を起こしやすい」という誤解を招くことにつながっているものと思われます。一方,犯罪の被害者が発達障害であったという報道は相模原障害者施設殺傷事件のようにセンセーショナルな事件以外はほとんどなく,被害者となるのはきわめてまれなことであるかのような誤解につながっています。
出典 精神医学 65巻5号 (2023年5月発行)松田 文雄
専門家の記事などを読んでいると、発達障害の特性自体が犯罪を引き起こすわけではないことがわかります。
発達障害を持つ子供は、相手の悪意や狙いに気づきにくいところがあるため、気を付けなければならないのは、むしろ犯罪被害者になることです。
発達障害自体が犯罪の原因になるわけではない。周囲の無理解などからくる逆境体験、さらにそういった体験に基づく二次障害を防ぐために、環境を整えることの重要性がわかります。
不安になる前に、私たち保護者がやるべきことが見えてくるのではないでしょうか。
前記の記事の中で塩川先生は、叱責より支援することの重要性を説いておられ、支援の方法や、言葉かけ、勉強法などを周囲の大人が学ぶことで、発達障害を持つ子供の非行や問題行動が減るのではないかとおっしゃっています。
支援方法、環境整備を私たちが学んでいけば、「犯罪者になるのでは」などと恐れるに足りないことがわかります。
いかがでしたか?
この記事が少しでもお役に立つことがあれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
<関連記事>