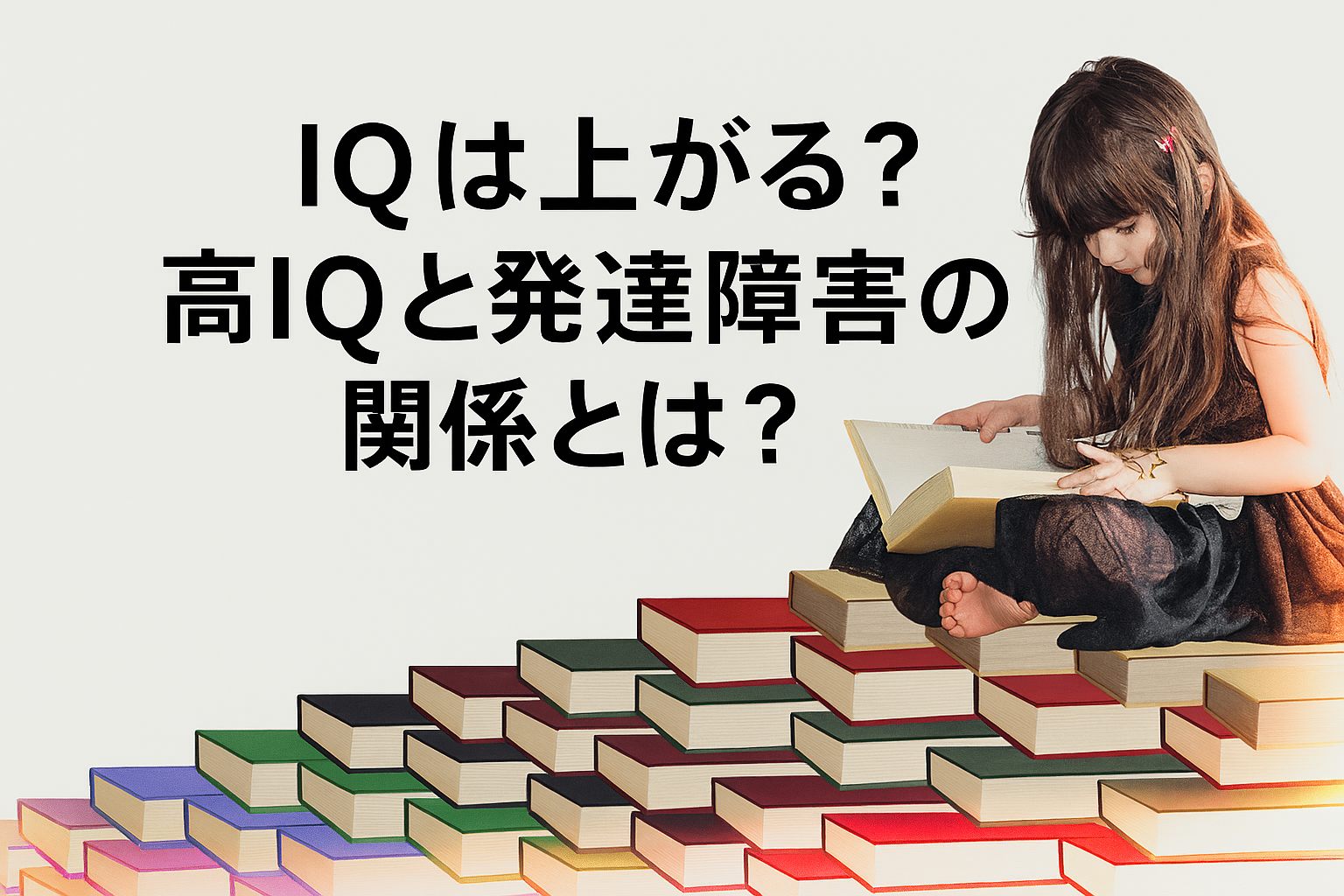<2025年10月更新>
発達障害(自閉症スペクトラム・ADHD)、グレーゾーンのお子さんについてよく聞くのが、
- 運動会でダンスを踊らない
- 練習が辛くて嫌がる
- 参加そのものを拒否する
といったお悩みです。
「無理に参加させるべき?」「休ませてもいいの?」と迷う保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
について実体験も交えて整理しています。
【PR】運動やダンスが苦手でも大丈夫。特性に合わせて練習できるマンツーマン体育教室。
🌿人気記事🌿
特性に合う習い事と教室・トラブル回避のコツ👇

運動会で踊らない・参加できない発達障害の子が抱える5つの理由
理由1:発達性協調運動障害(ダンスや運動の苦手さ)
最近の運動会は組体操が減り、その代わりにダンスが定番となっています。
しかし、発達障害のあるお子さんの中には、ダンスや体の動きを苦手とする子が少なくありません。
例えば、
- お手本を見ても体の動かし方が分からない
- 動きがぎこちなく同級生にからかわれる
- 「ふざけている」「やる気がない」と誤解されて先生に叱られる
こうした経験から「運動会が辛い」と感じる子もいます。
その背景にあるのが 発達性協調運動障害(DCD) です。
手先の不器用さや運動技能の弱さが特徴とされる発達障害の一種で、ASDやADHD、LDと合併することも多いと言われています。
不器用や運動音痴に該当する人はたくさんいますが、それが早期から極端に現れるのが特徴で、「極端で」「日常生活に支障が生ずる」ような場合には、この障害に該当することがあります。
該当するかの判断には専門医の診断が必要ですが、具体例を挙げてみます。
※これらの例に該当しても発達性運動強調障害にはあたらない場合も多いので、目安程度にご覧ください。判断には医師による診断が必要です。
また、靴ひもや箸、逆上がり、自転車などはできるようになる時期に個人差があります。単に時期が遅いからと言ってこの障害に該当するわけではないことも付け加えておきます。
理由2:集団行動が苦手
発達障害のあるお子さんの中には、根本的に集団行動が苦手な子もいます。
運動会では「みんなと同じ動きをすること」が求められるため、その特性が表れやすくなります。
例えば、
- 「みんなに合わせる」とはどういう行動なのかが分かりにくい
- そもそも集団行動をとる必要性を感じない
- 感情コントロールが苦手、衝動性が高い
といった特徴から、全体の流れに合わせることが難しくなる場合があります。
その結果、周囲と違う動きをして叱られたり、友達に注意されてトラブルになる、からかわれる、といったことから運動会が辛くなってしまうことがあります。
理由3:やる事がわかりにくい
発達障害のある子の中には、耳からの情報よりも、視覚的な情報の方が理解しやすいタイプの子がいます。
こうした子どもは、
- 口頭での説明は頭に残りにくい
- 手順や内容を「見て確認」できると安心できる
という特徴を持っています。
しかし、運動会の練習は普段の教室活動と違い、慣れない動きを口頭で指示されることが多いため、内容が理解しづらく、イメージを持ちにくい場合があります。
その結果、不安が強くなったり、活動を嫌がったりしてしまうこともあります。
理由4:見通しが立たず不安になりやすい
自閉症スペクトラム(ASD)の特性のひとつに「想像力の弱さ」があります。
そのため、ASDの子どもは経験したことのない状況や場所に置かれると、これから何が起こるのか分からず、不安や混乱を強く感じてしまうことがあります。
これは、発達障害のない人には理解しにくい感覚ですが、本人にとっては大きな負担になるそうです。
特に、運動会当日や練習を始めたばかりの頃には、
- 活動を頑なに拒否する
- 些細なことで怒ったり感情のコントロールが難しくなる
- 運動会と関係のないことに強くこだわる
といった様子が出やすくなります。
こうしたときは、お子さんが「見通しを持てない不安」に困っているサインかもしれません。
また、ASDに見られる「こだわり行動」も、同じ行動を繰り返すことで見通しを持ち、安心感を得ようとする心理が背景にあると考えられています。
理由5:感覚過敏(音や光などの刺激に弱い)
運動会では、大きな音や強い光、たくさんの人の動きなど、さまざまな刺激が一度に押し寄せます。
感覚が敏感なお子さんにとっては、これが大きな負担となり、参加を辛く感じる原因になることがあります。
「感覚過敏」とは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚のどれか、または複数が過敏で、日常生活にも困難が生じる状態を指します。
理解されにくいため「神経質」「大げさ」と誤解されることも多く、子どもは我慢を強いられてしまうのです。
例えば、聴覚過敏がある場合、
- 周囲の大きな応援の声
- スピーカーから流れる音楽やアナウンス
- 徒競走のピストル音
といった刺激が強すぎて、不安や緊張が高まったり、頭痛や吐き気など体調不良を引き起こすこともあります。
【PR】集団練習が苦手な子には、特性に合わせたマンツーマン体育教室がおすすめ。無理のないペースで少しずつ練習ができます。
運動会に参加できない・踊らない場合にできるサポート方法
運動会を「辛い」と感じる子にとって、周囲のサポートはとても重要です。
どのように声をかけ、環境を整えていけばいいのか――具体的な方法は 後編の記事 で詳しくご紹介しています。

運動会にどうしても参加したくないときは欠席してもいい?
「どうしても嫌がる場合、無理に参加させるべき?」
保護者が最も悩むテーマのひとつです。
欠席の可否や、その際に注意したいことについても、後編の記事 で体験を交えてまとめています。
🌈関連記事🌈
発達障害の子は運動音痴?家庭での対応と教室紹介【体験談】
発達障害の子が「運動が苦手」と感じる理由を整理し、家庭でできるサポートと安心して通える体育・スポーツ教室を紹介しています。