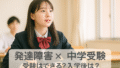<2025年10月更新>
本記事は、以下の記事の続き(後編)です。
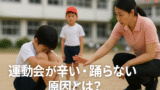
👆前編では、発達障害(自閉症スペクトラム・ADHD)、グレーゾーンのお子さんが「運動会を苦手」と感じる理由について、発達性協調運動障害や集団行動の難しさなどを体験談を交えて整理しました。
後編となる本記事では、
- 運動会が辛い、踊らない、参加できない場合の具体的なサポート法
- 「どうしても参加したくない」と言われたときの対応や気を付けたいこと
について、保護者の視点から整理していきます。
「子どもが運動会を嫌がるとき、どう支えたらいいか」「参加させるべきなのか」迷ったときの参考にしていただければ幸いです。
1. 運動会に参加できない・踊らないときの具体的サポート方法
<前編>では「なぜ運動会が苦手なのか」という理由を解説しました。
ここからは、実際に保護者ができる具体的サポートについて紹介します。
保護者が気を付けたいこと
発達特性を持つ子の運動会をサポートするために、保護者が取れる行動として、以下のようなことが考えられます。
- 子供の体調を整え、リフレッシュさせる
- 運動会について話を聞き、気持ちを受け止める
- 苦手なことや困っていることを先生に伝えて相談する
- 必要に応じて、子どもの特性に合った支援を先生にお願いする
ただし、ここで気を付けたいのは「どのような支援を行うかを最終的に決めるのは先生である」という点です。
サポートを決めるのは先生の役割
上に挙げた1~4のうち、4の「サポートを先生にお願いする」ことについては注意が必要です。
どのようなサポートを行うかは、子どもの様子や人員配置、競技の内容などを踏まえて先生が決定するものです。
そのため、保護者が具体的なサポートをお願いしたとしても、それが実際に行われるかどうかは先生の判断次第になります。
私自身の経験から言えば、3の「困っている様子や苦手なことを先生に伝えて相談」までをした後は、先生に任せて子どもの様子を見守る、という流れになることが多いと感じています。
また、サポートをお願いするときには、
- 前年の運動会で効果があった工夫
- 主治医や療育の先生など専門家のアドバイス
といった情報を一緒に伝えると、サポートに取り入れてもらえる可能性が高まります。
気持ちを受け止めるだけで解決することもある
「うまくできなくて悔しい思いをした」
「毎日しんどいけど練習を頑張っている」
こうした気持ちを保護者がしっかり受け止めてあげるだけで、お子さんが安心して頑張れることもあります。
「否定せず、まずは気持ちを受け止める」ことが大切です。
👇ここからは、保護者ができる具体的なサポートを整理します。
サポート① 苦手なことを先生に相談する
前編(運動会が苦手な理由①) でご紹介したように、運動会のダンスや組体操が苦手な理由の一つに発達性協調運動障害があります。
練習を続ければ改善することもありますが、本人が努力しても上達が難しい場合もあります。
そのため、練習が始まる前の時期(先生が振り付けやプログラムを考えている頃)に、どんな動きが苦手なのかを早めに伝えて相談しておくことがとても有効です。
もちろん必ず対応してもらえるわけではありませんが、先生によっては:
- 簡単なパートを割り当ててくれる
- 「この振り付けが難しい人はこちらでも大丈夫」と代替の動きを考えてくれる
といった工夫をしてくれることもあります。
また、先生に伝えておくことで、「真面目にやっていない」「やる気がない」と誤解されて叱られるのを防ぐ効果もあります。
さらに「ダンスが苦手で、からかわれるのを気にしている」と相談しておけば、先生が同級生の言動に気を配ってくれることもあります。
その一言があるだけで、子どもにとっては安心感につながります。
🌿人気記事🌿
発達障害の子におすすめの習い事・トラブル回避のコツ👇

サポート② 視覚な支援を取り入れる
発達特性を持つ子どもにとって、「口頭での説明だけ」では理解が難しいことがあります。
特に運動会のダンスや整列は動きが多く、耳で聞くだけでは覚えにくいものです。
そこで役立つのが 視覚的な支援 です。具体的には次のような方法があります。
- ダンスの振り付けを動画で配布してもらう(できるだけ早めに)
- 並び方や体形移動を図にして見せてもらう
- 立ち位置に目印をつけてもらう
- 準備や整列の手順も含めた詳細なプログラムを用意してもらう
こうした「目で見てわかる情報」があるだけで、不安がぐっと減り、安心して取り組める子は少なくありません。
また家庭でも、動画や図を繰り返し確認できるため、練習の効果が高まりやすくなります。
動画は早めにもらえると、ある程度頭に入った状態で自信を持って練習にのぞめます。
🌿あわせて読みたい
👉 発達障害の子も安心!英会話・英語教室おすすめ3選【ADHD・自閉症】
サポート③ 見通しが立たないときは予行演習や動画を活用
<前編>の運動会が苦手な理由4でも触れましたが、「先の見通しが立たないことへの不安」は、多くの子どもにとって大きなハードルです。
これは、場面をイメージする力が弱いという特性から生じることもあり、本番の様子がわからないと不安や緊張が高まり、参加しづらくなることがあります。
そこで有効なのが、予行演習への参加や過去の運動会動画の活用です。
- 予行演習で会場の雰囲気や流れを体験しておく
- 前年の動画を一緒に見て、本番の様子を具体的にイメージする
こうしたサポートによって、「当日の流れが見えない」という不安を減らし、安心して本番を迎えられるケースもあります。
なお、本番は観客の声援や視線などで雰囲気が大きく変わるため、予行演習と動画を組み合わせて事前にイメージを作るのがおすすめです。
サポート④ 感覚過敏はサポートグッズと静かな休憩場所
運動会では、ピストルの音や大勢の声、音楽、強い日差しなど、感覚的な刺激がとても多いため、感覚過敏のある子にとっては大きな負担になります。
最近では、徒競走のスタート音をピストルではなく笛などに変更してくれる学校も増えてきました。こうした対応が可能かどうか、事前に先生へ相談してみるとよいでしょう。
もし難しい場合は、ノイズキャンセリングイヤホンやイヤーマフなどのサポートグッズを活用する方法もあります。
競技中は難しい場合もありますが、応援や待機の時間に使うだけでも不安や疲労の軽減につながります。
また、出番の合間に休める静かな場所をあらかじめ確保しておくと安心です。
「ここに避難すれば大丈夫」という場所があるだけで、気持ちが落ち着きやすくなるので、先生に相談してみましょう。
✨ 学校行事だけでなく、日常の学びを支える環境づくりも大切です
👉 【発達障害と学習支援】おすすめ塾・家庭教師・オンライン教材の選び方
2. 運動会にどうしても参加したくないときは欠席してもいい?
ここまで、運動会に参加しやすくするためのサポート方法を紹介してきました。
それでもお子さんが、

運動会に参加したくない!
と言う場合もあります。
そんなとき、保護者はどのように対応したらいいのでしょうか。
まずは運動会に参加したくない気持ちを受け止める
「行く」「行かない」という決定を保護者の方がする前に、
まずは「参加したくない」という子どもの気持ちを受け止めることが大切です。
運動会に向けて練習を重ねていく中、園や学校では「運動会に向けて頑張ろう」という気運が高まっています。
お子さんは、大きな不安や罪悪感、焦りを感じているかもしれません。
勇気を振り絞って「参加したくない」と伝えているお子さんの気持ちを、一度受け止めてあげることが、まずは最も大切です。
受け止めるというのは、すぐに「休んでいいよ」と認めることではありません。
「君の気持ちはそうなんだね」と、とりあえず否定せずに思いを受け止めることです。
<気持ちを受け止めることがなぜ大切なのか>
保護者の方は「運動会に参加したくない」と言われて、ショックを受けるかもしれません。
「これから毎年欠席すると言い出したら…」など、いろいろ先のことを考えてしまうこともあるでしょう(私も同じ経験があるのでわかります)。
でも、こういうときはピンチのようであって、実は大きなチャンスなのです。
「辛いことを話せば受け止めてもらえる」
「勇気を出して言ったことを否定せず尊重してくれた」
「困ったことがあっても、相談すればどうにかなる」
親子の間に、こんな「信頼関係」を築くことができたら、この先もっと大変なことが起こっても、お子さんは親御さんに気持ちを話したり、相談しながら乗り越えていくことができるでしょう。
私は今、思春期まっただ中の息子を育てていますが、この「親子の信頼関係」と「困ったときに相談する習慣」に、とても助けられています。
思春期になれば、発達特性を持つ子といえども、親の手の届かない場所で活動することがどんどん増えていきます。
大学生や社会人になれば、もう親が口を出すことはほとんどできなくなるでしょう。
そんなときに役立つのが、「自分の力では対処が難しいと感じたときには、親や信頼できる人に相談する」という習慣と、親子の信頼関係です。
「運動会に参加したくない」と言われると、親も孤独で不安になります。
ですが、子どもの声に耳を傾け、気持ちを受け止める――その経験が、後の自分たちの背中を押してくれることにつながっています。
運動会に参加したくない理由を聞く
お子さんが落ち着いた状態のときに、運動会に参加したくない理由を聞いてみましょう。
- 何か困ったことがあるのか
- 運動会についてどう思っているのか
お子さんの言葉を遮ったり、自分の意見に誘導したりせず、ゆっくりと理由を聞いてあげることが大切です。
そのうえで、どうすればいいかを一緒に考えていきます。
「保護者の」運動会に参加させたい理由を見つめなおす
運動会に参加させるかを考えるときは、
保護者の方ご自身が、
「どうしてお子さんを運動会に参加させたいのか」
を一度見つめなおしてみてください。
「出席するものだ」という固定概念や、「ほかの保護者の目」にとらわれていませんか?
最も重視すべきは、参加する子どもの気持ちです。
確かに運動会には、子どもにとって良い面がたくさんあります。
- 友達と良い思い出を共有できる
- クラスの一体感を味わえる
- 役割分担の大切さを学べる
- 難しいことに挑戦する経験ができる
こうしたメリットはたくさんありますが、それは今年の運動会に参加しなければ得られないものでしょうか?
他の行事でも得られるかもしれませんし、本人がやる気になって臨んだ来年の運動会で得られる可能性もあります。
団結心やチャレンジ精神は、自分の意思で主体的に参加したときにこそ得られるものです。
以前私は、「今年の運動会を休んでしまうと、来年も休むのではないか」と心配したことがありました。
でも、それは取り越し苦労でした。
子どもは年々成長していきます。
種目が変わったり、成長によって辛さが軽減されれば、来年は参加したくなるかもしれません。
反対に、今年無理をして参加し、辛い思いだけが残ると、来年から参加できなくなる可能性もあります。
来年どうなるか…、それは今はわからないことです。
運動会は、保育園・幼稚園・小・中・高校を合わせると15回以上あるんですね。
息子の体育祭への参加は残り少なくなりましたが、振り返ると1回の運動会はただの通過点にすぎません。
長い目で見れば、運動会に参加できなかったとしても、悩みを相談して、周囲の大人が味方になってくれた、共に考えてくれたという実体験は、お子さんにとって大きな力になります。
ケースバイケースで簡単に答えが出ませんが、お子さんの気持ちを大事にし、必要なサポートをした上で出した結論であれば、大きく道を踏み外すことはないと思います。
🌟こちらの記事もおすすめ
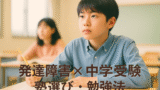
いかがでしたか?
この記事が、少しでもあなたのお役に立てばうれしいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。