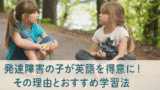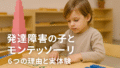<2025年10月更新>本記事はプロモーションを含みます。
本記事は、YouTubeチャンネル 「PIVOT」 の教育シリーズで放送された、東北大学教授・瀧靖之先生の回をもとにまとめています。
動画では「運動と楽器演奏が子どもの脳に与える影響」を、脳科学の視点からわかりやすく解説。
本記事ではその要点と家庭での実践アイデアを紹介します。
「習い事を通して子どもの可能性を伸ばしたい」と考える方におすすめです。
▼参考動画
【習い事の効果を脳科学者が分析】スポーツVS音楽|学力への好影響
1. 運動が脳を育てる理由
瀧先生が強調していたのは、「運動最強」という言葉。
運動は脳の海馬(記憶をつかさどる部分)を刺激し、記憶力を高めることが分かっています。
さらに、不安やストレスを和らげる働きもあり、学びやすい心の状態をつくる効果があるそうです。
1-1. 勉強前の運動が効果的な理由
【瀧先生のポイント】
勉強前に軽く体を動かすと、授業の理解度や集中力が上がるという研究結果があります。
たとえば海外では、1時間目の前に少し走るだけで成績が上がった例も。
運動は記憶を助けるだけでなく、ストレスを抑えて集中できる脳の状態を作ります。
1-2. 我が家の場合(朝の筋トレ習慣)
夫と高校生の息子は、朝にYouTubeの筋トレ動画を見ながら10分間のトレーニングをしています。
その後に朝食・身支度をする流れですが、息子は「1時間目から集中できる」とのこと。
夫も「朝の仕事がはかどる」と実感しているそうです。
夏休みなど長期休みも続けることで生活リズムが一定になり、「休み明けがつらい」という悩みも減りました。
男子は特に、筋トレやスポーツによる体の変化やホルモン分泌の促進が、メンタルの安定や自信の向上につながり、自己肯定感を高めるとも言われます。
2. 外遊びが自己肯定感を伸ばす理由
2-1. 自然体験が脳を育てる理由
【瀧先生のポイント】
外で体を動かすことは、自己肯定感を高める効果があるそうです。
自然の中で走る・登る・釣りをするなど、自分の力で達成する経験が「できた!」という感覚を育て、心の安定や意欲の向上につながります。
2-2. 我が家の場合(自然体験のすすめ)
息子の小さい頃の定番は、サップ・釣り・そり遊び・キャンプ。
発達特性があり育てにくかった時期も、大自然の中ではどんなに騒いでも大丈夫。
親子でのびのび過ごせる貴重な時間でした。
嬉しい効果を簡単にまとめます👇
●サップ(SUP)
・バランス感覚・体幹が鍛えられる
・意外と簡単に乗れることで自己肯定感アップ
・大自然の中で冒険気分を味わえる
・最近は体験ツアーなど手軽に挑戦できる機会が増加
●釣り
・生き物や自然環境への興味を育てる
・釣り堀やいけすなど気軽に体験できる場所も多い
●そり遊び
・雪の斜面を登ることで全身運動・足腰の強化
・滑る時はバランス感覚を養う
・雪の中で自然を感じながら遊べる
【PR】スキー・スノボツアーはこちらから👇
●キャンプ
・火起こしや調理、テント設営などを通して自分の役割を学べる
・自然の中での経験が自己肯定感アップにつながる
【PR】大変なキャンプ道具の準備、手入れから解放されます
ただし、キャンプ場によってはテント同士が近く、夜は静かに過ごすルールもあります。
お子さんの声が気になる場合は、コテージやグランピングがおすすめです。
【PR】ドーム、ヴィラ、コテージ様々なスタイルが選べます
<関連記事>親子でリラックスして楽しめる外遊びについて

3. 楽器演奏が脳に与える好影響
3-1. 楽器で鍛えられる脳の力
【瀧先生のポイント】
楽器を演奏すると、脳のさまざまな領域を同時に使うことが分かっています。
楽譜を見て覚え(ワーキングメモリー)、その通りに動かし(実行機能)、音を聞いて修正する(フィードバック)という複雑な働きによって、脳の可塑性(変化する力)が高まるそうです。
さらに、音を正確に聞き分ける力がつくことで、英語のリスニング力が上がるなど、語学面にも良い影響があります。
リズムを感じ取る力も育つため、運動や勉強の基礎づくりにもつながります。
3-2. リズム感は後天的に育てられる
【瀧先生のポイント】
リズム感は生まれつきの才能ではなく、後天的に育てられる力だそうです。
楽器演奏やリトミックのようにリズムを意識して体を動かすことで、脳の可塑性が高まり、そのリズム感が運動・勉強・会話など、あらゆる活動に役立つといいます。
また、話す・聞く・考えるといった日常の行動にもリズムがあり、リズム感が整うとテンポよく思考できる=頭の回転が良くなるとも。
3-3. 我が家の場合(ピアノとリスニング力)
息子がピアノを始めたのは、少し遅めの小学1年生。
手先を細かく動かすのはあまり得意ではありませんでしたが、「音感がいい」と言われる子でした。
そして高校生になった今、息子の得意科目は英語。中でもリスニングが一番得意です。
ピアノで培われた音感が、英語のリズムや発音を聞き取る力につながっているのではと感じています。
【PR】オールイングリッシュの本格派レッスンをオンラインで
<関連記事>発達特性を生かして英語学習を
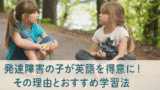
4. 子どもが「ハマる体験」を大切に
4-1. 模倣から学び、熱中する力を育てる
【瀧先生のポイント】
子どもは、親の行動や感情をまねて学ぶといいます。
脳の「ミラーニューロン」が働き、親が楽しそうに取り組む姿を見ることで、
子どもにも「やってみたい」という気持ちが自然に生まれるそうです。
スポーツも楽器も最初は模倣から始まり、まねを通して脳が発達し、技術が身につく。
つまり、親が楽しむ姿を見せることが、最高の学びのきっかけになるのです。
4-2. 我が家の場合(親がピアノを楽しむ姿を見せる)
息子が2歳の頃、音楽教室(リトミック)に通わせていた時期がありました。
けれども途中で「行きたくない」と言い出し、1年も続かずにやめてしまいました。
その経験から、音楽を習わせるのはもう難しいかもと思っていたのですが――
小学生になってから、私がピアノを弾く姿を見て「僕もやりたい」と自分から再チャレンジ。
それからは楽しく続けられるようになりました。
親がピアノを弾かなくても、兄弟・友達・先生など、身近な人が音楽を楽しむ姿を見せることがきっかけになります。
「楽しそう」が一番のモチベーションだと感じています。
【PR】🎻楽器がもらえるから気軽に始められます
<関連記事>ピアノが発達障害を持つ子に与える影響👇

5. まとめ
YouTube動画のサムネイルには「スポーツVS楽器演奏」となっていましたが、
瀧靖之先生の結論は「どちらも脳に素晴らしい効果がある」というものでした。
穏やかな語り口で、運動や音楽が子どもの脳をどう育てるかをわかりやすく紹介。
家庭で実践しやすい内容だったので、今回記事でシェアさせていただきました。
興味のある方は、ぜひPIVOTチャンネルの本編もご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
🌿関連記事🌿